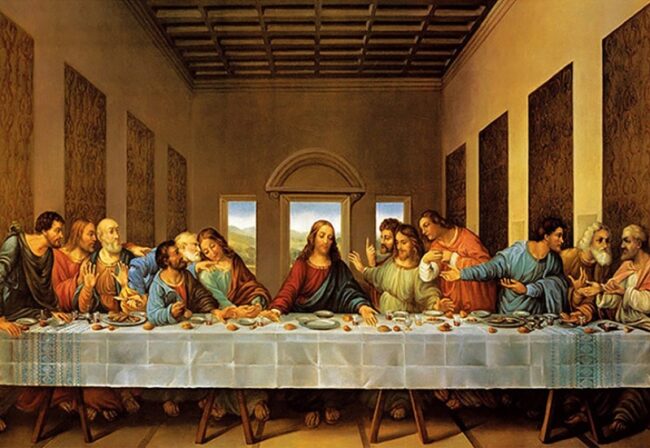新しく生まれるということ
聖書箇所:ヨハネの福音書3章1節~15節 メッセージ題目;新しく生まれるということ あれはうちの上の娘が生まれる少し前のことですから、もう16年も前になりますが、高校時代とても仲の良かった友だちが、突然亡くなるということがありました。当時日本は、リーマンショックのあおりをもろに受けていたときで、彼はというと、ある旧財閥系の証券会社で、課長代理の職にありました。もともと彼はその系列の総研で働いていたところ、まったく慣れない証券畑に出向になり、しかし、持ち前の真面目さで、35歳にして課長代理にまで登り詰めました。しかし、リーマンショックです。その責任感の強さ、真面目さが仇になったのでしょうか。まるで彼は、リーマンショックの責任を一身に背負って亡くなったかのようでした。 私は生前の彼に、とにかく福音を伝えようとしましたが、あと一歩のところで伝えきれなくて、ついに彼のことを信仰告白に導けませんでした。そんな悔恨を込めて私は、高校の母体であったお寺を会場に行われた彼の葬儀に出たのですが、抹香臭いことがあまり好きでなかった彼らしい葬儀でした。お香も焚かれず、お坊さんがお経をあげることもなく、参列者がお焼香をすることもありませんでした。 ただ、お焼香の代わりに献花は行われました。ところが、なんとその献花の間、会場の大きなスピーカーから、歌が流れてきました。中島みゆきの「時代」という歌です。彼はオフコースやさだまさしやチューリップが好きで、ニューミュージックの話もよくしていたので、いかにも彼らしいな、と思いましたが、その「時代」の歌詞に、私は胸を締めつけられる思いになりました。「まわるまわるよ時代は回る 別れと出会いを繰り返し 今日は倒れた旅人たちも 生まれ変わって歩きだすよ」この歌がお寺の中で流されたということは、仏教的にはこの死生観が正しいということなのでしょうか。しかし、聖書のみことばはそんなふうに教えているものか。彼は今、いったいどこにいるんだ。あらためて、彼を信仰告白に導けなかったことを、大いに悔い改めさせられました。 今日のテーマは「新しく生まれるということ」です。中島みゆきの歌が受け入れられるような土壌の日本では、イエスさまのこのおことば、聖書の教えも、誤解されかねないのではないでしょうか。新しく生まれる、それは神の国に入るために必要なことです。しかし、新しく生まれるとはどういうことか、どうなることが新しく生まれることなのか、それを押さえておかないで、ただ、日本人的な心で、雰囲気でこのことを捉えてしまうなら、下手をすると、ことは自分に永遠のいのちがあるかどうか、わからなくなってしまう、という、重大な問題になってしまいます。 こういうことを申しますのも、ここ10年、20年の間に、韓国で脅威となり、日本にも上陸して久しいある種の異端は、「何年何月何日にあなたは救われましたか?」とクリスチャンに質問し、うまく答えられないと、それがわかっていないとは、救われていないということです、とおどかし、自分たちこそほんとうの救いに導きます、と、自分たちへとオルグします。その結果、そのクリスチャンは、気がつくとその異端の手先になってしまっているわけです。彼らの信じているものは、イエスさまのようでいて、イエスさまとはまったくちがうものです。そんなことにならないためにも、聖書の語る「救い」ですとか「新しく生まれること」といったものをしっかり押さえておく必要があります。 それでは本文に入りましょう。1節です。……このみことばは、以下15節までつづく場面に登場するニコデモを紹介する節ですが、この箇所からわかることは、彼がパリサイ人の一人だということです。律法を守り行うことによって神からの救いを得るよう教える律法学者、それがパリサイ人で、ニコデモはそのパリサイ人だったということです。 また、ユダヤ人の議員、とあります。日本も近いうちに参議院議員選挙がありますが、あのように、ユダヤにも日本でいえば国会にあたる議会がありました。もちろん、ローマ皇帝やユダヤの分封王ヘロデのような権力者が上に君臨しているにはいますが、ユダヤの議会はその君主のもとにあって、政治的権力を行使する機関でした。最大定員は71名です。 その構成員は、祭司階級のサドカイ人、また、民の代表者である長老、そしてパリサイ人であったわけですが、ニコデモはその中でも、パリサイ人の一員として議員をしていました。つまり、ニコデモは国家の政治的指導者を兼ねた宗教指導者だったわけで、相当高いポジションにいたということになります。 さて、「ニコデモという名の人がいた」という表現は、ちょっと注意が必要です。それは、この箇所でわざわざ「人」と断っていることは、それに先行する2章23節から25節のそれぞれの節に出てくる「人」と関係があるからです。先週も学びましたが、ユダヤ人たちはイエスさまの行われたしるしを見て、イエスさまを信じました。しかし、イエスさまは彼らのその信仰を信頼なさいませんでした。彼らの心の中を見抜いておられ、その信仰が本物ではないことを知っておられたからです。そして、そのような人間に、わざわざご自身のことを何かほめてもらうようなことばなど、イエスさまは一切、必要としていらっしゃいませんでした。 そして、「ニコデモという名の『人』」という表現は、ニコデモもまた、イエスさまが信頼されなかった「人」、心のうちにあるものが何かをイエスさまに知られていたその「人」のひとりであった、ということを意味しています。その前提で2節を読みましょう。 ニコデモはまず、夜、イエスさまのもとを訪ねていきました。これは明らかに、パリサイ人として宗教論争を挑んだり、罠にはめたりするためではありません。イエスさまの教えを聴きに行くためです。しかし、イエスさまの教えを公然と聞くことは、立場上できませんでした。 2000年前のことですから、いかに都会でも、街灯がそこらじゅうを煌々と照らしていたりなどということはありません。ともしびを掲げて、足元もおぼつかない中、夜目(よめ)に隠れてやってきました。イエスさまがすでに、神聖なるエルサレム神殿で派手な大立ち回りを行われたことは、もちろん宗教指導者の知るところです。言ってみればこの青年イエスは、宗教指導者たちに睨まれた危険人物です。そんなイエスさまのことを白昼堂々訪ねることは、ニコデモが議員やパリサイ人としての地位や体面を保つうえで、何ひとつプラスになどなりません。 しかし、ニコデモはほかのパリサイ人とちがい、イエスさまはただの教師、ラビではない、という確信がありました。それで、夜なのにもかまわず、お訪ねするという行動に出ました。ニコデモはまず、イエスさまに、「先生」と呼びかけていますが、これはユダヤ人の宗教教師に対して用いる尊称「ラビ」です。日本の教会では、牧師だけではなく、牧師按手を受けていない伝道師、一般信徒である日曜学校の教師、みんな「先生」と呼ばれますが、韓国では牧師にかぎった呼称で「モクサニム」という呼び方があります。「モクサニム」は、牧師以外には一切使いません。それと同じように、宗教社会であるユダヤで「ラビ」と呼びかけるのはかなり特別なことです。いわんやイエスさまは、公的に宗教家になるための教育を受けたことがないことを、宗教指導者たちは知っていました。そのようなイエスさまに「ラビ」と尊敬を込めて呼びかけているのですから、よほどのことです。 さて、ニコデモがイエスさまのことを「ラビ」とお呼びし、そればかりか「神のもとから来られた教師」とさえ、下にも置かないような美辞麗句を並べている理由は、「しるし」にありました。ニコデモはイエスさまが行われた数々のしるしを見て、人間業では到底できないその奇跡を行われているゆえに、イエスさまが神のもとから来られた「ラビ」であると認めているわけです。ニコデモのこのことばは、そんな「神がかった」すばらしいラビだからこそ、私はもっとあなたから学んで、律法に対する理解を深め、もっといい教師になりたいのです、という、期待感を読み取ることができます。 しかし、そんなニコデモに、イエスさまはおっしゃいます。3節です。あなたはわたしのことを、神から来た教師と見込んで教えを請いに来ていますね。それではあなたに最も大切なことを教えます。人は、新しく生まれなければ、神の国を見ることはありません。 さて、この「新しく」ということばですが、たしかにそれは「新しく」という意味はあるのですが、原語にはもうひとつ、「上から」という意味も含まれています。 新しく生まれる、ということは、日本人が漠然と信じているような、「来世」という概念とは根本から異なります。中島みゆきの歌の「時代」は、いのち果てる人にとっての「来世」を意識した歌ではないかと思いますが、聖書は、そういう漠然とした「来世」ではなく、もっと実際的ないのちの実在を語っています。上から新しく生まれた人が、神の国を見る。そうではない人は、神の国をまだ見ていない。 神の国を見る。それは、「私の」神が「私を」統べ治めるその実際を、「私が」見ている、ということを意味します。たとえば私たちはいま、日本にいますが、これは言い換えれば、「日本国を見ている」ということです。それは地理的なテリトリーということもそうですし。日本語という共通語、また、日本の法律、行政、警察、国防のもとにいるということでもあるわけです。意識するにせよしないにせよ、私たちは有形無形に日本国を「見ています」。 しかし、ユダヤに関してはどうでしょうか。確かに神さまは、イスラエルと契約を結ばれたゆえ、そのイスラエルの末裔であるユダヤにも依然として契約は有効です。しかし、そんなユダヤ人がユダヤの地理的、政治的、宗教的テリトリーの中にいるからといって、ユダヤ人に生まれついたら100パーセント、神の国を見ているということにはなりません。彼らは、イエスさまを神の子として、金輪際認めませんでしたし、ということは、イエスさまの父であり、イエスさまをこの地にみこころをもってお送りになった神さまのことを信じてなどいなかったことになるからです。ユダヤ人の間にはただ、創造主への形ばかりで中身のない信仰があるだけです。彼らも異邦人同様、上から、すなわち神によって新しく生まれなければ、神の国を見ている、すなわち、この地上にあっても神のほんとうのご支配を認めていることにはならないわけです。 そこでニコデモが返します。4節。小学生のとき、友達とふざけて言いあった冗談を想い出します。例の水戸黄門の「この紋所が目に入らぬか!」(目のところに印籠を持っていって)「入らないよ。」新しく生まれるとはどんなことか、みことばから学んでいる私たちには、ニコデモの言っていることは屁理屈のように聞こえるかもしれませんが、これは、「新しく生まれる」というおことばに、「上から」という意味も含まれていたことを見落としていたことから生まれた勘違いといえるわけです。 また、ニコデモのことばには、霊的なことを、唯物論的に解釈しようとして無理をする人間の限界も見ることができます。みことばというものは子どものようにただ素直に受け入れればいいものを、あれこれ人間的な理屈、解釈を加えるものだから、わかるものもわからなくなってしまいます。そういう人にぴったりのことわざがあります。「下手の考え休むに似たり」。問題は、勉強してきた人ほど、なまじ自分には知恵があると思うものだから、自分のことを「下手」と認められなくて、結果、休むことにも劣るような無駄な考えで時間も体力も浪費する、ということです。 しかし、イエスさまはさすがです。わざわざ夜道を歩いて教えを請いに来た者を「物わかりの悪い者は立ち去りなさい」などと追い返すお方ではありません。もっと懇切丁寧に教えてくださいます。5節です。水と御霊によって生まれる。今日はペンテコステ、御霊、聖霊さまがこの地にくだり、教会が誕生したことをお祝いする日ですが、聖霊なる神さまは人を上から、つまり神によって、霊的に新しく生まれさせてくださいます。 では「水」とは何でしょうか。私たちバプテスト教会がとても大事にする、バプテスマに必須の水のことでしょうか。たしかに、公式に教会のひと枝としてクリスチャンになるには、バプテスマという形で水に全身を浸します。これはバプテスマのヨハネ以来のもので、イエスさま自身もバプテスマをお受けになり、また、イエスさまは弟子たちを主導されて人々にバプテスマを授けさせておられたことから、バプテスマが「新しく生まれること」に必須ということを、イエスさまが認めておられたのはたしかです。 しかし、ここでいう「水と御霊によって」の「水」は、バプテスマという儀式に用いられる「水」という以上の意味があります。 近いうちに私たちはヨハネの福音書の4章を学びますが、そのみことばには、人目を忍んで真昼の暑いさなかに水汲みに来た女の人に、イエスさまがこんなことをおっしゃっている場面が登場します。「この水を飲む人はみな、また渇きます。しかし、わたしが与える水を飲む人は、いつまでも決して渇くことがありません。わたしが与える水は、その人の内で泉となり、永遠のいのちへの水が湧き出ます。」同じくヨハネの福音書の中で、7章にはイエスさまがエルサレム神殿で参詣客に向かって堂々とお語りになるメッセージが登場しますが、このようにおっしゃっています。「だれでも渇いているなら、わたしのもとに来て飲みなさい。わたしを信じる者は、聖書が言っているとおり、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになります。」続く節で、それがイエスさまのお受けになる御霊のことを意味していると解説していますが、ともかく、水とは、イエスさまのもとに行って飲むものであり、また、そのことは、御霊と密接な関係があります。 イザヤ書44章3節のみことば、水というものと霊というものを並行して語っています。霊とは神の民イスラエルの子孫に祝福をもって注がれるもの、その一方で、水とは潤いを失った民、渇く民を潤すものです。その水を与えるのがイエスさまであり、イエスさまが来られたことは、このイザヤ44章3節のみことばが成就したことを意味します。つまり、水と御霊によって生まれるとは、御霊の導きにより、いのちなるイエスさまに出会い、イエスさまのみことばをいただき、イエスさまの御名によって祈ることによって、イエスさまと交わり、イエスさまだけが与えてくださる永遠のいのちの中に、永遠にとどまりつづけるものとなることを意味するわけです。 6節。仮に、ニコデモが「そんなことはありますまい」とばかりに質問してみせたようなこと、母の胎から生まれ直した、などということが起きたとしても、それはしょせん、肉によって肉が生まれたことにすぎません。しかし、霊によって生まれることをさせてくださるのは聖霊なる神さまです。人間的ながんばり、たとえば聖書勉強や断食祈祷、多額の献金のようなことを一生懸命やれば、それで100パーセント、霊的に新しく生まれるなどという保証はどこにもありません。しょせんそれが人間的な修行の範囲を出ないものなら、なおさらそうです。 7節。なぜ、ニコデモはこのことを不思議に思ってはならないのでしょうか。それは、目でその存在を見ることを許されない霊なるお方である神さまのことを学び、語り、教える者ならば、霊によって霊なる神さまを理解していてしかるべきである、もし、霊によって神さまとそのみこころを理解できているならば、このようなことをそもそも不思議に思う余地などないからです。しかし、ニコデモは神のことを、まだ肉的なレベルでしか悟れていませんでした。 8節。「霊」ということばは原語で「プニューマ」といいます。これは「風」と同じことばです。イエスさまはコアな弟子たち以外に神の国というものを説明されるとき、たとえをお用いになるのが常でしたが、ここでもたとえを用いていらっしゃいます。しかも、「霊」と同じ「風」です。霊は風とよく似ているというわけです。ぴったりのたとえをお話しになります。風は思いのままに吹く、しかし人には、それがどこからどう吹いているかわからない。御霊もそれと同じ。 風が吹いたら桶屋が儲かる、ということわざは、風が吹いたら埃が舞う、あれよあれよという間に桶屋が儲かる、というわけですが、風は目に見えなくても、それが吹いたら、目に見える環境に確実に影響を及ぼします。そのように、目に見えない御霊が働かれるとき、人に御霊の実が結ばれ、愛する、喜ぶ、平安になる、人に寛容になる、人に親切にする、人に善意をもって行動する、人に誠実になる、柔和になる、自制する、それらのことが実現するような、イエスさまに対する信仰を持って、罪赦され、救われ、神さまの子どもとなり、永遠のいのちをいただき、神の国を見る……聖霊さまは、目に見えなくても、ほんとうにすごいお方なのです。 しかし、それらのみわざを主導されるのは、神さまのみこころです。人間的に何か計画したところで、そのようなことが実際に起こるわけではありません。だれが、いつ、どこで、どのように、なぜ、御霊の働きを体験して信仰を告白し、御霊の実を結ぶか、それは神の主権の中でなされるみわざです。 そういう前提に立つと、私たち、いま信仰を確かに持っている者たちが、いつ、どこで、どのように信仰を持ったかを具体的に、細かく記憶しているかどうかということは、実はそんなに大事なことではないことがわかります。大事なのは、「いま救われているかどうか」、もっといえば、「こんな私のことを神さまが救ってくださったと、いま信じているかどうか」ということです。ですから、その日時を細かく突っ込んでクリスチャンを動揺させるような異端には、くれぐれも引っかからないことです。 しかし、9節をご覧ください。ニコデモはぽかんとしています。それはそうなのです。ニコデモが拠って立ってきた教えは、いかに律法を正しく守り、神に認められる人になれるか、ということであったからです。つまり、救いとは人間の側の努力にかかっている、という前提で神の教えを理解してきたわけです。ニコデモがイエスさまのことを神のもとから来られた教師と見込んで、教えを請いにやってきたということは、私はもっと正しくありたい、もっと正しく律法を守り行いたい、もっと確実に努力したい、そうして救われて神の国を見る者となりたい、という思いがあってのことでした。 しかし、イエスさまのお語りになることは、ニコデモの拠って立つ前提を、根底から覆すものでした。人間の頑張りではなく、神の霊が新しく生まれさせる? そんな莫迦な! ニコデモは茫然としました。 しかし、イエスさまは容赦されません。10節。こんな厳しい言い方でニコデモをお叱りになったのは、この程度の宗教指導者が高い所からユダヤの民を教えているようなら、民がみことばのほんとうに語ることを理解することなど、金輪際ありえないからです。イエスさまは、民が羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れていたのを見て、はらわたもよじれんばかりに深く憐れまれましたが、民がそうなってしまったのは、羊飼いであるべき宗教指導者たちが、正しく羊を養えるだけの力を持ち合わせていなかったからです。ニコデモもまた、ユダヤ人という名の羊の群れを衰えさせた張本人であったのです。イエスさまの怒気を含んだようなおことばは、ご自身の羊を放っておく牧者への怒りの現れでもありました。 11節。イエスさまはここで、「わたしたち」とおっしゃっていますが、これは、「父、御子、御霊」の「わたしたち」とも取れますし、イエスさまがそのおしえを授けた弟子たちと形づくる共同体とも言えます。いずれにせよ、「わたしたち」と複数形になっているのは、ニコデモも含めたユダヤの宗教指導者の陣営と対立しつつ神の側に立つ陣営、ということを意味します。 その「わたしたち」が知っている、見ている、ということは、つまり、イエスさまがご存じで、ご覧になっていることを、神の陣営で共有しているということを意味します。ここにいる私たちもキリストのからだなる教会ですから、もちろん、この「わたしたち」に含まれるべき存在です。 それをニコデモのようなパリサイ人、宗教指導者たちは、神のみこころをだれよりもよく知っているという立場に自分たちのことを置く以上、神の子なるイエスさまがお認めになるレベルで、充分に知って、受け入れている必要がありました。ところが彼らはイエスさまの御目には、まったくそのレベルに達していなかったのでした。 12節。御霊の働きの主体は神の領域に属するものの、その実践される現場は地上です。地上に住む人に御霊は働かれ、信仰を持たせ、新しく生まれさせ、永遠のいのち、神の国に入れてくださるからです。しかし、いやしくも神の律法を取り扱う教師を自称する教師ならば、それよりさらに深い神の奥義、それこそ一般人のレベルでは地上からはうかがい知ることのできない天上における神のみこころに通じているという確信があるべきです。しかし、イエスさまから見れば、地上における御霊の働きもわからない教師たちは、天上のことなど教えてもわかるわけがない、ということです。 13節。天上のことが人に分からないのは、天に上ったことのある人がいないからです。ところがイエスさまは、ご自身は天から下った人だから、天上のことがわかる唯一の人であるとおっしゃいます。その、天上における父なる神さまのイエスさまに対するみこころは何か、それをイエスさまは14節、15節でお語りになっています。 出エジプトの旅程で、神に対して不平を鳴らし、神さまが民を養ってくださる不思議な食べ物「マナ」のことを、言うに事欠いて、「飽き飽きするみじめな食べ物」と言い放ったイスラエルの民に、神は怒りを発せられ、イスラエルのただ中に「燃える蛇」を送られ、それが人にかみついて多くの者が死にました。それを悲しんだモーセが神さまに祈ると、神さまは青銅で蛇をつくり、それを旗竿の上に掲げよと命じられました。それを仰ぎ見た者は蛇の毒が解毒し、死なないですみました。 そのように、青銅の蛇を旗竿の上に掲げて、人を死のさばきから救い出して生かすように、わたしは十字架に上げられて死ぬことによって、そして死とよみから上げられて復活することによって、さらには地上から上げられて御父の右の座に着き、地上の民が救われるようにとりなして祈ることによって、人を救う、それを信じる者はみな、わたしにあって永遠のいのちを持つのである、というわけです。 私たちクリスチャンは、キリスト教という「宗教」を信じて救われているわけではありません。「神さま」を信じていると言えるには言えますが、それはクリスチャンにかぎった話ではありません。いえ、クリスチャンに限った話で「神さま」を信じているといっても、それでも不十分です。十字架、復活、昇天をもって「上げられた」イエスさまを信じていること、それが私たちを救うことです。 私たちの読む聖書は分厚いですから、こんな細かいことが理解できるか、いわんや守り行えるか、と思いますでしょうか。しかし、信仰の道というものは驚くほど簡単、単純なものです。信じるだけ、これだけです。具体的には、みことばに書いてあることをそのまま、そのとおりです、と信じ告白することです。 今日はペンテコステ、聖霊さまがお下りになったことを記念する日ですが、私たちを救いに導く信仰は、聖霊さまが主体的にくださるものです。私たちはだれも、好きこのんでイエスさまを信じたりなどしません。なぜなら、例外なく罪人である私たちを支配する肉の思いは、御霊の願うことに真正面から逆らい、けっして従おうとしない、従いたくない、だから、従うことなどできないからです。 それが、イエスさまを信じていること、ゆえに救われていること、そして、さらに霊的に成長したいと願うことは、これはもう、神さま、聖霊さまのお働きとしか言いようがありません。だから私たちは、神さまにすべてのご栄光をお帰しするのです。この恵みをもって私たちの信仰を成長させてくださり、私たちの周りにいるひとりでも多くの人を救ってくださるように祈りましょう。