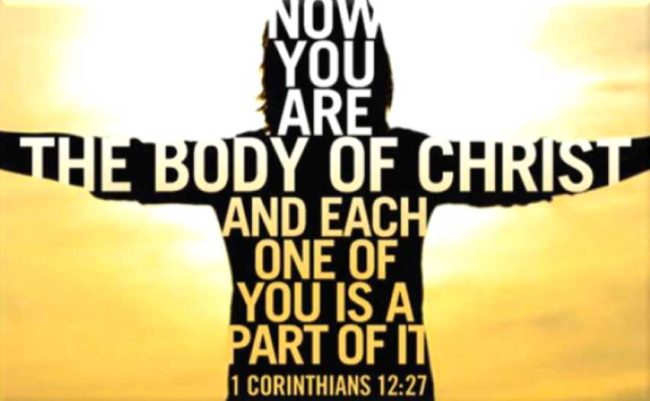いちじくの木の教え
聖書本文;マルコの福音書11章12節~25節 メッセージ題目;いちじくの木の教え 神さまの創造の不思議というものに、私たちはときどき出会います。たとえば、人のように見えるもの。それは、木ではないでしょうか。教会の駐車場に生えているような、植物の木。幹は胴体、太い枝は腕、そして、上のほうで茂る枝葉は全体が人の頭のように見えないでしょうか? ときどき絵本などで見ませんか、人のように顔があって、ことばをしゃべる木を。 逆に、これは以前学んだマルコの福音書のみことばにありましたが、イエスさまに目をいやしていただいた盲人が、最初人を見たとき、人が木のようです、と言っています。人の姿はぼんやり見ていると、木に似ているというわけです。 そういうわけで、神さまは人に似たものとして、木というものを創造されました。そういう木に囲まれて生活している私たちですから、たとえば春になると満開の花を咲かせるさくらの木が、寿命が来てこのままだと倒れて危ないからと、電動のこぎりなどで切り倒す現場に出くわすと、私たちはどこか心が痛みます。そんな私たちが何の予備知識もなく、今日の箇所を読んだらどう思うでしょうか? お尋ねしたいのですが、みなさまが最初この箇所を読んだとき、どんな印象をお持ちになりましたか? イエスさま、おなかがすいているからって、何もそこまでしなくても、などと思いませんでしたか? 正直に申しまして、私は最初そう思ってしまいました。 イエスさまは貧しい人や、からだの不自由な人をお心に留めてくださる、やさしいお方です。そんなイエスさまが時に、暴力的とさえ思えるような行動に出られるのを福音書で目にしたら、私たちは戸惑いませんでしょうか? 今日お読みしたみことばでは、イエスさまは木を枯らされただけではありません。エルサレム神殿の中で暴れ回っておられます。こんなイエスさまのお姿はあまり見られないだけに、目を丸くしてしまわないでしょうか? だからこそ私たちは、このようなイエスさまの行動から学ぶために、聖書を深く知る必要があるわけです。聖書に書かれていることを表面的に受け取り、かわいそう、とか、ひどい、とか、感情的に反応したら、下手をするとつまずき、信仰がそれ以上成長しなくなる危険があります。つまずかないために、主のみことばは愛に満ちた誤りなき神のことばであると受け取りつつ、謙遜に学ぶ姿勢が必要です。 さて、朝になってエルサレム城外のベタニアからエルサレムに入られるイエスさまは、その途上、おなかがすいておられました。折しも、遠くにいちじくの木が見えました。しかしその木は、葉が茂っているばかりで、何の実もついていませんでした。イエスさまはこのいちじくの木を呪われ、今後おまえの実をだれも食べることのないように、とおっしゃいました。 しかし、この13節のみことばを見てみますと、「いちじくのなる季節ではなかった」からいちじくの実はなっていなかったということが書かれています。それなら、実がなっていないのはしかたがないのではないでしょうか? イエスさまはそれをご存じなかったのでしょうか? イエスさまはひどいのでしょうか? 私も長いこと、この謎がわからずにいました。しかし、私がこの教会にやってきて、前任者だった宇佐神実先生にいただいた本、『聖書の世界が見える・植物編』という、もともとが漢方のお医者さんで、現在はイスラエルで宣教師をしておられるリュ・モーセ先生という方がお書きになった本を読んで、長年の疑問が氷解しました。今からお話しする、いちじくに関するお話は、その本を参考にお話しすることです。 多くの人はこのできごとを合理的に説明しようと試みて、大きく分けて2種類のことを言います。ひとつは、イエスさまがあまりにおなかがすいていて、いらだちのあまり呪われた、もうひとつは、十字架の死を前にして、瞬間的に理性を失われた。とくに後者の解釈は、かのシュバイツァー博士も採用しているものです。 しかしもちろん、そういう軽薄な理由でイエスさまがこのような行動をお取りになったわけではありません。そのために理解すべきことは、イスラエルにおいていちじくがどのように実を結ぶかということです。イスラエルは地中海の気候で、4月から10月までの乾季と、その残りの期間の雨季に分かれます。6か月の雨季の冬の間、葉のない枯れ枝のまま冬を過ごしたいちじくの木は、過越が近づくにつれ、わずかな葉とともに最初の実をつけ、その後長い夏の間に、5回にわたって実をつけます。じつは、初なりのいちじくを指すヘブル語と、夏の間に実るいちじくを指すヘブル語は、別のことばなのです。初なりのいちじくは「パーグ」、そのあとのいちじくは「テエナ」です。 つまり、これはヘブル語の原語に忠実に解釈すると、イエスさまが探されたのは「パーグ」、すなわち「初なりのいちじく」であり、しかし「テエナ」の季節ではなかった、ということです。過越の時期に葉ばかりが茂って初なりのいちじく「パーグ」がついていない木は、明らかに問題がありました。こんな木は夏になっても「テエナ」の実を結ばないことは明らかでした。 イスラエルにおいて果物とは基本的に夏のもので、冬には果物は実を結びません。初なりのいちじくとは、まさにイスラエルの民が待ち焦がれている甘いもの、滋味豊かなものであり、神さまがイスラエルの民に注がれるそのおこころは、この待ち望まれているもの、初なりのいちじくに例えられます。 義人が消え去ってしまった南ユダ王国の時代の預言者ミカ、偶像礼拝がはびこったヤロブアム二世の時代の北イスラエル王国の預言者ホセアが、神さまのその御思いを語りましたし、一方で南ユダの預言者イザヤは、その活動していた時代にアッシリアによって滅ぼされた北イスラエルを、はかなく食べられてしまう初なりのいちじくになぞらえました。 このように、いちじくの実は神の民の状態を象徴していましたが、同時にいちじくの木は、季節の訪れを告げました。特に、夏の訪れを告げます。マタイの福音書24章23節と24節のみことばに注目しましょう。イエスさまが終末のしるしについてお語りになっているとき、唐突にいちじくの木の話が出てまいります。これは、イスラエルにおいては秋が一年の四季の始まりであり、秋、冬、春と来て、最後が夏、すなわち、夏という季節は、イスラエルの人たちにとっては終末を意識させるものだからです。 その終末に、滋味豊富で、イスラエル民族にとっては最高の果実ともいえるいちじくの実のような実りがないならば、そのような者は木が枯らされるように、神の国から放り出されてしまいます。このイエスさまのみわざは、マタイの福音書ではひとつづきのように書かれていますが、時系列で理解するならおそらくマルコの福音書の順番どおりです。すなわち、イエスさまがいちじくの木を呪われたらすぐにたちまち木が枯れたというよりも、イエスさまが呪われたあとになってもう一度その木を見ると、枯れていた、ということです。たった一日で枯れたわけですから、マタイの福音書の表現、たちまち枯れた、ということばも、あながち間違っていないことになります。 ともかく、いちじくの木が枯れたことがわかるまでには間があるわけですが、その間何があったのでしょうか? そのできごとから何をお教えになるため、イエスさまはいちじくの木を枯らされたのでしょうか? それは、いわゆる宮きよめでした。イエスさまがエルサレム神殿にお入りになると、そこにはいけにえにする鳩を売ったり、両替をしたりして儲ける者たちがいました。要するに、神殿を世俗的な商売の場としていたわけです。 もし、彼らに言い分があるとすれば、礼拝者の献金は両替してやらなければならないじゃないか、いけにえを用意できない人もいるじゃないか、とでもなるでしょうか。 しかし、イエスさまはお許しになりませんでした。それは、神への礼拝さえも肉的な利得の手段とするほどに堕落した、過ぎ越しにふさわしい初なりの実を結ぶことから程遠い、神の民のなれの果てでした。イエスさまは暴力的とさえ思えるような手段を用いてさえ、彼らに制裁を加えました。 イエスさまは彼らのしていることに対し、本来、御父の家、すなわち祈りの家と呼ばれるべき神殿を、おまえたちは「強盗の巣」にした、となじっておられます。神殿は単なる宗教施設ではなく、神の民が祈りというつながりをもって神を父とする家庭を築く「家」です。神の民は祈りによって父とつながり、お互いが神という父を介してつながる家族です。それが実現する究極の場所が神殿です。そういう生き方をすることによって、やがて世をさばくさばき主としてこの地に来られるイエスさまにまみえることに、神の民たる者はともに備えるべきなのです。 ところが彼らのしていることは、そんな神の民とは似ても似つかない姿です。いえ、およそ人に生まれたならば、その創造主なるイエスさまの再臨に備えて、つねに父なる神さまと祈りをもって交わり、ものの売り買いを介してではないとつながれないようなドライかつ世俗的な関係ではなく、主にあってほかの人たちと愛にあふれた交わりを持つ共同体を形づくるべきです。つまり、彼らは人でさえありません。家ではなく、「巣」に住むようなけだものにも等しい者ども、そして、いけにえにするには鳩しかささげられないような貧しい者たち、巡礼に来ていてなけなしのお金を差し出そうとする人たちさえ利得の手段にするような彼らユダヤ人は、強盗だとおっしゃっているわけです。人のものを奪う、すなわちそうすることで、神のものを奪う彼らは、祈りの家に居座る強盗どもです。 過越とは、神のさばきと贖いの告げ知らされる大事なときです。このときイエスさまは、十字架におかかりになり、過越における究極の子羊のいけにえとなられました。しかし、その子羊によって贖われるべき肝心のユダヤ人は、御父の家、祈りの家を弱者から搾取してむさぼる利得の手段にして恥じることをしない、強盗どもと化していました。そんな彼らはうわべだけを誇る、過越の季節にふさわしくなく、まるで真夏のように葉ばかり青々と茂らせても、イエスさまを満足させる小さな実ひとつ結べない者たちでした。イスラエルの夏に象徴される終末が現に臨んでいようとも、そんなことはお構いなしの傲慢きわまる態度です。 ただ、イエスさまはいちじくの木を枯らされたことに対して驚いている弟子たちに対して、そのような霊的な奥義を説明される代わりに、信じて祈る者の祈りを神さまは聞いてくださる、山に向かって動いて海に入れ、と祈っても、そのとおりになる、と、すごいことをお語りになりました。 イエスさまのこのおことばを表面的に受け取るならば、そうか、そんな不可能と思えるようなことでも、信じて祈れば聞いていただけるのか、という理解で終わってしまいます。これは前に、岡野俊之先生という牧師先生のメッセージでお聴きしたことですが、岡野先生はまだ若者だったとき、この箇所から解き明かされたメッセージを聴いてイエスさまを信じ、家に帰ってノンクリスチャンのお父さまに興奮してお話しになったそうです。「お父さん、イエスさまを信じるってすごいよ! イエスさまを信じて祈るならば、山も動かせるんだよ!」すると、お父さまはこうお答えになったそうです。「馬鹿だなあ。おまえは自分の寝ていた布団ひとつ動かせないじゃないか。」要するにお父さまは、布団の上げ下ろしもできない者が、何が祈りの力だ、とおっしゃりたかったわけです。だから、ここでイエスさまがおっしゃりたかったことを、クリスチャンは祈れば必ず全能の力が与えられる、というレベルで捉えないことが大事になります。 これは、イエスさまがなぜいちじくの木を枯らされたか、そのことで弟子たちに何をお教えになろうとしたか、を考えることで理解すべきことです。海とは何でしょうか。神なき暗黒の世界の象徴です。しかし終わりの日、天国が実現したら、以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはやそこには海がないとみことばは語ります。それでもそうなる前に、エルサレムという山の町がもろとも海に投げ込まれるがごとく、主の時の訪れを無視しつづけて神の領域を強盗のごとく占拠しつづける、名ばかりの神の民のつかさたちは、海に投げ込まれるがごとく、火と硫黄の池に投げ込まれます。 その主の正義のさばき、御怒りの報復の日は必ず起こる、と信じて祈ることが、あらゆる祈りの基礎となります。その中には、人間的に考えたら不可能と思えることさえ含まれるでしょう。その祈りが聞かれることで主のご栄光が広くたたえられ、主の御国が拡大し、主の再臨が確実に近づくからです。 そう、私たちにとっていちばん信じるべきことは、主が必ずこの世界をさばき、天国を実現してくださるということです。しかし、あらゆる宗教や唯物論が常識となる一方で、再臨のイエスさまのご存在を頑として受け入れないこの世界において、このことを事実と信じて祈る求めることには、並大抵ではない信仰が必要とされます。何よりも、いちじくをたちまち枯らされたほどのイエスさまがどれほど全能なお方であり、また主権者であられるかを心の底から認める謙遜さ、敬虔さが必要とされます。イエスさまなど再臨するものかという間違ったこの世の常識に、どんなことがあっても負けない、いえ、むしろ私たちの祈りの力によって、再臨を確実に実現していただく、そのように信仰を働かせてまいりたいものです。 ただし、そのように全能の御手を伸ばしてくださる信仰を私たちが働かせるにあたって、イエスさまが命じておられることがあります。それは、兄弟姉妹を赦す、ということです。私たちは神さまから見ればあまりに罪が多く、神に敵対する歩みを意識するしないにかかわらずしている罪人です。そんな私たちはしかし、イエスさまの十字架によって、完全に罪なきものと見なしていただきました。しかし、そのように罪を赦していただいただけの私たちが、もしほかの兄弟姉妹の罪に目を留めて、怒ったり、さばいたりして、赦さなかったらどうでしょうか? よくもそんなことをしてくれたな、と、呪ったりしたらどうでしょうか? 神さまはそんな私たちのことをお赦しになりません。そんな怒りとのろいをいだくものは、天国にふさわしくないからです。 しかし、私たちはそう簡単に怒りを手放せません。しかしこのままでは、終わりの日に神さまが実現してくださる天国に入れません。ならば私たちは、天国を実現する全能の御業をなしてくださいという祈りを手控えるべきなのでしょうか? そうなってはなりません。むしろ私たちは、天国がわが身にも完全に実現するために、怒りを手放し、兄弟姉妹を赦す決断をする必要があります。それがもし極めて難しいこと、不可能なこととさえ思えるならば、そこにこそ私たちは、全能の御手を求めましょう。主は、不動の山のように居座る私たちの怒りさえも手放せるように、全能の御業をなしてくださいます。 ともに祈りましょう。私たちはひとりの例外なく、さばき主なる主の御前に立つ日が来ます。しかし、私たちはさばかれません。なぜなら、イエスさまの十字架によって罪を赦していただいているからです。この罪の赦しが、私たちの愛する人、まだイエスさまに出会っていないけれども私たちの愛している人に実現すること、それによって神の怒りからその方が免れられるようにと願いましょう。そして私たちは、人間的にはありえないことのように見えるイエスさまの再臨を、心から信じて求めましょう。