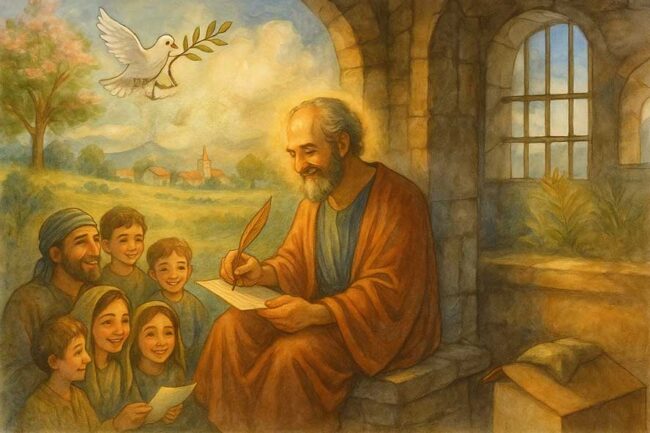御父の約束が叶えられる祈り
聖書箇所:使徒の働き1章1節~14節 メッセージ題目:御父の約束が叶えられる祈り 本日から毎月第1主日を基準に、「使徒の働き」の学びをいたします。使徒の働きはもともとの聖書では「使徒行伝」と呼んでいました。聖書の訳によっては「使徒言行録」という題名もついています。イエスさまに任命された使徒たちは、イエスさまが語られたように神の国を宣べ伝え、イエスさまが行われたようにしるしを行なって、神が私たち人間のうちに生きて働いておられることを証ししました。その記録がこの「使徒の働き」という書、使徒行伝、使徒言行録というわけです。 まず、今日の聖書箇所、1節から14節までをじっくり見てまいりましょう。1節と2節、これは、使徒の働きの著者が「テオフィロ」という人物にこの書をささげている、いわゆる「献呈辞」にあたるものです。実は、旧新約聖書66巻の中で、献呈辞の形式を取ったことばで始まっている書は、「ルカの福音書」と「使徒の働き」だけです。そしてその献呈先は、どちらも「テオフィロ」です。ルカの福音書がルカという名前の医師によって書かれたように、使徒の働きも同じルカが書いています。この献呈辞に出てくる「前の書」とは、ルカの福音書のことです。この「テオフィロ」はどういう人物だったか、諸説あります。実在の人物だったともいわれていますが、詳しいことはわかっていません。 しかし、こういう学説もあり、それは無視できないと考えます。「テオ」とは「神」、「フィロ」とは「愛」という意味です。「フィロ」の動詞形である「フィレオー」は、神の愛で愛する「アガパオー」には及ばないものの、愛する、という意味で、復活されたイエスさまに対してペテロが告白したことば「私があなたを愛することは、あなたがご存じです」の「愛する」が、この「フィレオー」です。そのように見ると、この「テオフィロ」という人が、実在した特定の人物であったにせよ、そうでなかったにせよ、この「使徒の働き」という書は、「神を愛する人」に献呈された書である、と言えるわけです。 私たちは、イエスさまが私たちになさったように、神さまのために実際にいのちを捨てて神さまを愛するなど、とてもできないかもしれません。しかしそれでも、私たちが神さまを愛していることは、神さまがご存じで、神さまは私たちのその愛を認めてくださっています。その信仰をいただいているから、私たちは恐れないで、神の御前に徹底して生きることができるのです。神さまを愛させてくださる、神さまの愛と恵みに感謝しましょう。 その、神を愛する私たち神の民にこのみことばをささげたのは、確かにルカではあります。しかし、聖書のほんとうの著者は、神さまです。神さまが私たちに、わたしのいのちを得よ、まことのいのちを得よ、永遠のいのちを得よと、私たちを大事に思って「献呈」してくださったのだとするならば、なんともったいないことでしょうか。神であるイエスさまがしもべとなって仕えてくださった、それはみことばを語って、私たちを生かしてくださることによってでした。私たちが神さまのためにすることは、もったいなくも私たちを大事に思って、神さまが私たちにささげてくださった、このみことばを読むこと、読んで、永遠のいのちに生きることです。それが、神さまに仕えることです。 3節、神のみことばがささげられたといえば、神のみことばが人となったイエスさまは、そのいのちをささげてくださいました。そういう意味でも私たちはもったいない恵みをいただいています。しかし、イエスさまは復活されました。いま私たちがお読みしているみことばは、イエスさまが復活されたことを体験した証人たちの証言です。 しかし、そのことを伝えさえすれば、人は「証人」になれるわけではありません。イエスさまが父なる神さまとその御国を宣べ伝えるお働きをするにあたっては、どうしても必要なお方がいらっしゃいました。そのお方が、人がみことばを宣べ伝える人になるために、つまり、キリストの証人となるために必要なのです。 4節と5節。イエスさまは聖霊によって、父なる神さまとその御国を宣べ伝えられました。そのように、宣べ伝える人になるには、聖霊なる神さまが注がれ、満たされ、遣わされる必要があります。聖霊の注ぎ、満たし、派遣を体験し、確信していないならば、その人はどんなに聖書の知識があっても、どんなに善行に富んでいても、キリストの証人になることはできないのです。 父なる神さまは人に、聖霊のバプテスマを約束してくださいました。イエスさまの証人になるには、罪深い肉がキリストとともに十字架にくぎづけになり、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きているという、その生きた告白が内側から湧き出るほどの信仰をいただく必要があります。その信仰をもつことを可能にするのは、私たちの努力や修練ではありません。聖霊さまを求めることです。 イエスさまがこのとき、あなたがたはそこを離れてはいけません、とお語りになった場所、エルサレムとはどんな場所でしょうか? イエスさまが十字架にくぎづけにされて死なれ、そしてよみがえられた場所です。およそ人にとって信仰というものは、十字架につけられ、復活されたイエスさまに始まります。まずそこにおいて、父の約束を待ちなさい、とおっしゃるのです。その約束とは、間もなく、聖霊のバプテスマを受ける、ということです。 主が命じられた場所にともにとどまり、御父の約束を信じ、その約束の成る時を待ち望む。そのために彼らが取る行動はひとつ、ともに集まって祈り、その約束を成し遂げてくださいと祈ることでした。 しかし、使徒たちにはすぐには、イエスさまのおっしゃることが理解できていませんでした。6節。彼らはなお、イスラエルがローマの圧政から独立し、目に見える独立国家となることに関心がありました。それはその当時のユダヤ人ならみなそう考えていたと言えることでしょう。 しかし、7節です。イエスさまは使徒たちのそのことばを、頭ごなしに否定はなさいません。イエスさまは、イスラエルがやがて国として再興されることは、御父のご計画のうちにあることを明らかにされました。しかし、その時がいつなのかということは、御父がご主権をもってお決めになることであって、あなたがた人のあずかり知るところではない、とおっしゃいます。 人は時に、神さまのみこころと関係なく、自分なりの解釈で物事を理解しようとしたり、予測したりします。だから、私たちはいついかなる時も、先入観や思い込み、人間的な願望も含め、自分の考えを下に降ろし、神さまとそのみことばに自分を明け渡し、みことばに示されたみこころに合わせていく必要があります。それでこそ、私たちは主のご主権がその人生に顕される、ふさわしい歩みをすることができます。 8節のみことばです。父なる神さまの権威は、目に見えるイスラエルが、それこそこのときの使徒たちが期待したように、人間的な主権国家として立てられること以上に、まことのイスラエルなる神の国が、働き人に聖霊が注がれ、聖霊が満たされ、そして彼らが遣わされ、神の子イエスさまが十字架につけられ、ゆえにそれが指導者から大衆に至るまでに目撃された、エルサレムに始まり、そこからユダヤ、サマリア、ひいては世界の果てまで、イエスさまが神の御子、救い主、王の王であると証言する証人となる、そのことにおいてあらわされます。 父なる神さまは権威をもって、イエスさまを王としてお立てになりました。イエスさまが王として、主として統べ治められ、宣教のわざによって救われた者たちも、イエスさまとともに統べ治める王となる。このことにこそ、父なる神さまの権威があらわされます。いかなる意味であれイスラエルが再興されることは、権威をもってすべての上に臨まれる御父のみこころにかなっていることです。しかし、それ以上に御父の権威があらわされることは、私たちが宣教のわざによって救われ、御国の民となり、救われたすべての民が御父の権威のもとにひれ伏すことです。 そのわざは、繰り返しになりますが、聖霊なる神さまが御父と御子から送られ、主導されることによって成し遂げられます。宣教の主人公は、有名だったり、話術が巧みだったり、知識が豊富だったり、何やらオーラが漂っていたりする働き人ではありません。聖霊なる神さまです。私たちは聖霊なる神さまに用いていただく器にすぎません。 ちょっと注意すべきことを付け加えますが、私たちはよく、有名な牧師のような働き人を指して、「主に大きく用いられている聖霊の器」などという言い方をします。いい呼び方ですし、働きの主人公が聖霊なる神さまであるということからすれば、それは確かにそうなのですが、注意が必要です。この言い方は下手をすると、「聖霊に強く臨んでいただく資格のある偉大な人物」というニュアンスを帯びかねません。それでは、その人物の栄光が現れるのであって、三位一体なる神の栄光が現れていることにはなりません。崇高なことばも、単に人をほめる動機で濫用していないか、気をつける必要があります。 ともかく、宣教の主人公である聖霊に用いられることは、すなわちそれは、神との交わりの中で神さまご自身とそのご栄光を人々の前に顕すことであり、およそ人間にとって最高の生き方です。ただしこの生き方は、ひとりでするものではなく、聖霊によってイエスさまを主と告白し、その告白をもってキリストのひとつからだとされた、教会という共同体のなすわざです。 イエスさまはこの、最後の約束をお語りになるや、たちまち天の雲の中に引き上げられ、見えなくなりました。天への栄光の凱旋です。しかし、使徒たちはそのイエスさまの挙げられた天を見つめてばかりはいられませんでした。彼らが心に留めるべきは、この地上にて栄光をもって生きられたイエスさまが、同じ姿でまた、この地上に戻ってくる、再臨です。再びイエスさまが来られるまで、彼らは、イエスさまがこの地上においてせよと命じられた、宣教の働き、言い換えれば、主のご栄光を表す働きを、最後の最後まで、いのちのバトンをつなぎながら、世界中にて展開する必要がありました。 もちろん、ここにいます私たちも、信仰の先輩たちからその、宣教というバトン、神の栄光を顕すというバトンを引き継ぎ、次の人にバトンを渡す役割をいただいています。宣教は、聖書に示された救いの原理を論理的に説明する「福音提示」をすることにかぎりません。もちろん、それは大事ですし、それを教わっていなければ、人はイエスさまを信じることはできません。しかし、福音を伝えようという私たちが、聖霊の交わりに生きていない、ということは、往々にしてあることです。そういう人にとっての伝道というものは、人から立派なクリスチャンとして認められたい、という、実は肉的、宗教的な野心から出ていたりしないでしょうか。表では立派なことを口にしていても、心の中、人の目につかないところでは、不従順、不信仰をやめないでいる、それは、聖霊の交わりに生きていないということです。 しかし、聖霊の交わりに生きるならば、私たちは喜んでみこころに従いますし、従えないでいるために葛藤する悩みをもし持っているならば、主に切に祈り、その弱い領域にご介在いただいて、みわざが現わされます。そこから私たちは、たとえ宣教師のように上手に福音提示ができなかったとしても、その、聖霊が主人公として生きてくださる人生を通して、キリストの証人として立派に用いていただけるのです。 彼らはその、聖霊に生きていただく、働いていただく、その生き方に献身することがみこころと知るとすぐ、ともに集まり、心を一つにして、御父の約束である聖霊のバプテスマを切望して、祈りはじめました。場所は「泊まっていた屋上の部屋」です。ここはもしかしたら、ほどなくして聖霊のバプテスマを体験することになる、マルコの実家の部屋かもしれませんし、イエスさまが使徒たちと最後の晩餐の時間を持たれた、二階の大広間かもしれません。いずれにしましても、あるいはそうでなかったとしても、彼らがいたところは「奥まった部屋」でした。祈るならば偽善者の真似をしないで、人目につかないところで祈りなさい、という、イエスさまのみことばに従順になったためともいえるでしょうが、彼らにはまだ聖霊が注がれていなかったので、大胆に人前に出る力がありませんでした。ともかく、祈りは人目につかないひそかなものでしたが、しかし、聖霊に飢え渇いての熱い祈りとなり、そう祈るように、主は彼らをお導きになりました。 私たちが求めるべきは、聖霊です。私たちの信仰生活が、どこかで頑張りすぎていなかったか? どこかで疲れていなかったか? どこかで退屈になっていなかったか? どこかで形だけのものになっていなかったか? どこかで神さまよりも人を意識していなかったか? どこかで神さまに対して間違ったとらえ方をしていなかったか? それは、聖霊の交わりを充分に求めないまま、というより、聖霊に明け渡す生き方をしないまま、宗教的な生活をすることに汲々としていたからではないでしょうか? この時間は、一緒に集まって聖霊さまを求める、聖霊さまに私たちを明け渡す、またとないチャンスです。今こそ祈りましょう。共同体全体がキリストの似姿に変えられ、私たちの行く先々で主の栄光を顕す、キリストの証人として用いられるものとなりますように。