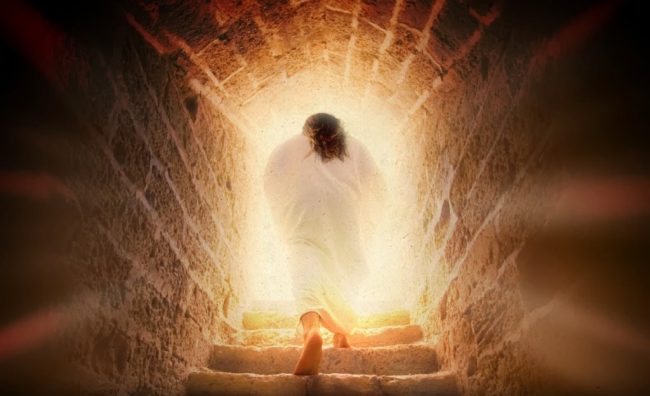反面教師の親、模範的な親
聖書箇所;サムエル記第一2章12節~21節 メッセージ題目;反面教師の親、模範的な親 昨日私と妻は、「わたしのかあさん」という映画を観に行ってきた。知的障害を持った親を葛藤を抱えながらも受け入れられるようになるにつれ、成長していく少女の物語である。この作品を見ると、人はたとえ知的障害を持っていようとも素晴らしい存在であり、大きく用いられる、という、勇気づけられるメッセージを受け取れる。何といっても、どんなに母親に対して悲しんだり、怒ったり、呆れたりする娘のことを変わらずに愛しつづける母親の姿にとても感動した。ほんとうに、教会のみなさまにご覧いただきたかった。機会があればぜひご覧いただきたい。 そんな映画の余韻に浸りながら、私は母の日を迎えた。ああ、そういえばうちの母にもしばらく電話していなかったなあ。親孝行しなくちゃなあ。そんなことも思う。今日、母の日に、私たちは親というものについて考えていこう。 聖書は親子関係というものについても扱っているが、今日はその中から、サムエル記第一の最初の部分から学びたい。サムエル第一、それは預言者サムエルと、そのサムエルに油注がれて王となったサウル、そしてダビデについて語るみことばだが、サムエル記第一の最初の部分は、サムエルがどのように生まれ、神の人として立てられ、育てられてきたかを語っている。 その、サムエルの生い立ちに対し、対照的な姿で登場するのが、サムエルの母であるハンナを導いた祭司エリの息子、ホフニとピネハスである。今日の箇所は、神の人として立てられ、育てられながら、あまりに対照的だったこの両者を育てた親の様子から、親というものは主の御目にどのようであることがふさわしいか、特に今日が「母の日」であることから、サムエルの母ハンナの立場に注目して見てみたい。 12節。彼らはよこしまな者たち、とあるが、新改訳聖書の欄外脚注にあるとおり、これは直訳すると「ベリヤアルの子ら」となる。ベリヤアル、とは、「無益な、悪い、役に立たない」という意味であり、したがって彼らは、無益な子、悪い子、役に立たない子、というわけであった。祭司としてハンナとサムエルの親子を霊的に導いた父親エリとはまったくちがう、役立たずの子ども、というわけだった。 なぜ彼らはそのように悪く、無益で、役立たずだったのか? それは「主を知らなかった」ということばに集約されている。別の訳の聖書を読めば「主を知ろうとしなかった」とある。彼らはちゃんと祭司という肩書を持っていた。ハンナとサムエルの親子をりっぱに導けるだけの霊的指導者、エリを父親に持っていた。彼らは主を知り、みことばを学ぶ環境においては最高だった。なのに彼らは学ばなかった。学ぼうとしなかった。 いったい、何が彼らを、主を知ることから遠ざけていたのか? それを説明するのが13節以下のみことばだが、早い話が、彼らは民のささげる肉のいけにえを横取りして、いけにえとして焼き尽くして主にささげることをせず、むさぼり食うことをしていたのだった。 そのことを17節では、彼らホフニとピネハスが「主へのささげ物を侮った」と総括している。これがどれほど大きな罪か想像できるだろうか? いけにえとしてささげる家畜は、初子の最良のものでなければならない。ちょっとでも傷があったり、障害があったりするものは、ささげてはならない。 家畜を飼う者たちとしては、初子、はじめて生まれた子どもたちは、とても愛おしい存在ではないだろうか。しかもその中でも、傷のない完璧なもの……しかし、それを惜しげもなくほふり、焼き尽くすということは、最良のいけにえをどうか主に受け入れていただきたいという、切なる献身の現れである。 いけにえを焼き尽くす炎を見るとき、イスラエルの民は、痛みの伴った献身を果たすことができたことに、心からの感謝を主におささげしたことだろう。主よ、あなたさまはこうして、私の献身を受け入れてくださいました! 感謝します! それが何か。その肉を焼き尽くすことをしないで、勝手に肉を取って食べるわけである。俺は生の肉を食べるぞ、ということは、焦げて食べられなくなった肉ではなく、少し焼いていかにも香ばしい肉を食べるわけである。いけにえになるのは最良の家畜ですから、それを焼いて食べたらおいしくないわけがない。だが、それは焼き尽くしてささげるものであり、みな主のものである。祭司とは、そのようにして民のささげ物を主にささげる役割をする立場にあるのに、その肉を神さまになり代わって食べようというのだろうか。神さまにささげる最高の礼拝を私利私欲のために横取りしようというのだろうか。 祭司の子は祭司、という、世襲は、残念ながら主に対する敬虔さ、また恐れというものまで伝えてはくれなかったようである。だが、ホフニとピネハスの発言に、とても気になる表現がある。15節を見るとこのようにある。 「人々が脂肪を焼いて煙にしないうちに祭司の子はやって来て、いけにえをささげる人に、「祭司に、その焼く肉を渡しなさい。祭司は煮た肉は受け取りません。生の肉だけです。」と言うので、とあるが、自分たちのことを肩書で「祭司は」と言っていることに、注意が必要である。自分たちのことを肩書で呼ぶなんて、いかにも自分が霊的に特別な存在だとでも言いたいのだろうか。 ホフニとピネハスはエリにとって次世代にあたるが、次世代がしっかり育つ上で、私たち年長の世代の者たちの責任は大きい。反面教師として、ホフニとピネハスの父親であるエリの場合を見てみよう。エリは、ホフニとピネハスがいけにえの肉を横取りしていること、そればかりか、神殿で仕える女性たちに姦淫の罪を働いている、ということを聞いた。だがエリは何と言っているか? 24節。……うわさが悪いから彼らが悪いのか? いや、人のうわさが彼をさばくのではなく、神が彼らをさばく。ホフニとピネハスがそのような罪を犯していることを、神殿の責任者であり、ホフニとピネハスの監督者でありながら普段から見抜けなかったエリにも大きな問題がある。いえ、見抜けなかったどころか、そのようなよこしまな指導者を、エリは親として育ててしまったわけである。 25節のエリのことばを見よう。……確かに、言っていることは正論である。しかしよく見てみよう。何かおかしくはなかろうか? 仲裁に立つ存在はいないわけではない。私たちには仲裁に立つ存在がおられる。それはイエスさまである。イエスさまは十字架にかかってくださり、神と人との仲裁の役割を果たされた。ということは、こんなことを言うエリは、祭司でありながら、キリストが見えていなかったことになる。神に対して人が犯す罪を仲裁される存在であるキリストに出会えなかったならば、祭司である自分自身も罪人ゆえに神の御前にへりくだって出るべきであることがわからなくなってしまう。エリは、子どもたちを救い主に出会わせるという、本来もっともすべきことができていなかったのである。 百歩譲って、この時代はイエスさまが生まれるはるか前の時代だった、だからエリにキリスト理解がなかったのは当然ではないか、と考えてみよう。しかし、それまでの時代にも、救い主キリストを見せた役割をした人はいて、祭司ともあろう者なら、そういう人たちをとおして、救い主キリストが見えていなければならなかったはずである。例えばモーセがそうだった。神を捨てて金の子牛を礼拝した民を滅ぼすとおっしゃった神さまに、いえ、むしろ、私の名前こそいのちの書から消していただきたいと懇願した。それをお聞きになった神さまは、イスラエルを滅ぼし尽くすことをなさらなかった。アブラハムもそうだった。ソドムとゴモラを滅ぼすと告げられた神さまに何度も交渉して、10人の正しい人がいれば滅ぼさないでいただきたい、と条件をつけ、神さまから約束を引き出した。神さまはその祈りに応え、ロトを救われた。 こういうケースを、エリが知らなかったはずがない。しかもモーセやアブラハムの場合は、自分が罪を犯さなかったのに、身代わりとなって神さまに懇願したわけである。エリはどうか。このようにホフニとピネハスを育ててしまったことに対する悔い改めが先立ってしかるべきではないか? その上で、神さまに対して自分自身が、親として、霊的指導者として、仲立ちに立つ祈りをささげるべきではなかったか? みことばがわからなかったという点でも、子どもたちの罪の責任を負おうとしなかったという点でも、エリは親としてふさわしい役割を果たすことができなかった。 ここで、もうひとりの親、サムエルの母、ハンナのケースを見てみよう。 ハンナはエルカナという男性の妻だった。しかし、エルカナにはもうひとり、ペニンナという妻がいて、このペニンナには子どもがいた一方で、ハンナには子どもがいなかった。子どもがいないということはその頃、祝福が臨んでないことと見なされていた。そんなハンナはエルカナに愛されていたが、ハンナのことを、子どもがいないという理由でペニンナはいじめた。 この一家は、毎年1回、主の神殿に参詣することを常としていた。そう、エリの親子が仕えていた神殿である。エルカナの一家は、それほどまでに主に敬虔な家族であったが、ともに主の前にこの家族が出るとき、ハンナは否が応でも、子どものいないわが身の悲しさを思ったことだろう。 ハンナは思いあまって、泣きじゃくって神さまに祈った。まるで酔っ払いのように取り乱して祈った。しかし、その祈りの内容が振るっていた。生まれた子どもを主にささげるというのである。そう、子どもは私のものとしてほしいのではない、あなたのものとして、あなたの必要のために送り出します、というのであった。 そして神さまはハンナの祈りを聴き届けてくださり、子どもを授けてくださった。ハンナは祈って誓願を立てたとおり、サムエルを神さまにささげた。具体的には、祭司エリのもとで、主の献身者、すなわち祭司になるための教育を受けさせた。それも、乳離れしたらすぐにサムエルをエリのもとに住まわせるという徹底ぶりであった。 それでも、ハンナは母親であることをやめたわけではなかった。ハンナは年ごとの神殿における礼拝に赴く際、幼いサムエルのために小さな上着をつくり、持っていってやった。 その小さな上着を縫ってやっているハンナの気持ちを考えてみよう。先週の礼拝で、初穂とは最良のものであると学んだが、サムエルを神殿に送ったということは、ハンナにとって最良の初子のいけにえ、奇蹟をもって応えられたたましいをささげたということである。 その息子とつながれるのは、この母親の祈りをこめて縫い上げた服……それを着ていてくれるならば、母と息子はつながっていられる……どんな気持ちでハンナはこの服をつくったことだろうか。肉親としての息子に対する愛情を注いだという意味もあるが、息子といういけにえをより神さまに受け入れられるにふさわしく整えたという意味もないだろうか? そんなハンナが、じっくりつくり上げた小さな上着を手にして神殿に参詣し、献身者として成長するサムエルを見たら、どんなにうれしかったことだろうか? 私たちの小さなころを思い起こしていただきたい。幼稚園や小学校の名札、体育着には、お母さんがていねいに名前を書いてくれた。そんなお母さんは普段、学校という場所には決して入ることができない。しかし、子どもを人として整えてもらうために、あえて幼稚園なり学校なりに送り出す。子どもの持ち物を親が用意してあげることは、そんな、会えない子どもと親をつなぐ絆のようなものではないか。 そんな親の楽しみにしているもののひとつが、授業参観である。子どもの置かれている現場にまでやってきて、そこで子どもがどのように育てられているか、さらには用いられているかを見ることは、親として大きな喜びというしかない。私は昨日子どもの授業参観に行ってきた。普段、思いを寄せていても決して入れない場所に行ってきたわけである。親として用意してやった制服に身を包んで子どもが授業を受けるさまは、見ていて感動を覚える。先生が生徒たちに課題を出して、それを一斉に解かせるとき、うちの子どもの鉛筆は動いているかな、と見守るのは、なかなかハラハラドキドキの体験である。しかし、こうして学校という現場で育てていただいていることはとても感謝なことだと感じるしかなかった。 幼いサムエルに小さな上着を持っていってやるハンナがその神殿でささげる祈りは、やはりサムエルのことであっただろう。その母の祈りに主はお応えになり、やがてサムエルは全イスラエルをさばくリーダーとなり、果てはダビデ王を立てる神の器となった。 ハンナの熱い祈り、ハンナの献身を主は喜んで受け入れてくださり、サムエルに代わる子どもを授けてくださった。あの、どんなに祈っても子どもが産めず、夫の無理解、もうひとりの妻のいじめに耐えてきたハンナのことを、ついに主は顧みてくださったのだった。 とは言っても、だいじな初子を神さまにささげたという事実に変わりはない。その献身に導かれるのは、実に大きな恵みなしにはできないことである。 サムエルは、エリのような愚鈍な霊的指導者、ホフニとピネハスのようなならず者の先輩に囲まれ、霊的指導者として訓練されるうえで、条件はよくなかった。しかし彼は、すばらしく成長し、神と人とに愛されたとみことばは語る。その背後にはハンナの祈りがあった。 サムエルは、エリが愚鈍な指導者だからとか、父親失格だからといって、霊的な指導を軽んじることをしなかった。語られることばのみを、乳飲み子が乳を慕い求めるように、しっかりいただいて、霊的にすばらしく成長した。彼を神の人にしたのは、母のとりなしの祈り、そして、その祈りの中で育てられた、主ご自身に対する態度だった。 私たちはどうだろうか? エリやホフニやピネハスは、いわば反面教師である。このような霊的な愚鈍さ、むさぼりを、私たちのうちから除き、サムエルのようになりたいものである。そしてハンナのように、私たちキリストにある兄弟姉妹は主にささげられていることを心から認め、お互いが主にささげられている「生きたいけにえ」としてふさわしい生き方ができるように、次世代を育ててまいりたい。母の日、それは次世代の親の役割を果たすべき私たちが、次世代を覚えて祈る日である。 また、母の日は、親という存在をとおして神さまがどんなに私たちひとりひとりに「愛」というものを教えてくださったかを覚える日である。私たちの中には、お母さんは明確な信仰告白をしないままお亡くなりになったという方がおられるかもしれない。いわゆる「毒親」としか思えない母親のもとで不幸な育ち方をしたとしか思えない方もおられるかもしれない。しかし、どんなお母さんであれ、お母さんをとおして神さまがこの世界に生を享けさせてくださり、育ててくださったという事実に変わりはない。それでもお母さんを赦せない人は、その怒りを主の御手に委ねる選択をしていこう。しかし、神さまがお母さんをとおして私たちをここまでにしてくださったという、この恵みに感謝し、世界のお母さんたちが(お父さんたちも!)みこころにかなう人になれるように、次世代を神の子どもとして育てる人になれるように、祈ろう。 https://www.youtube.com/watch?v=0Ay710qiQrc