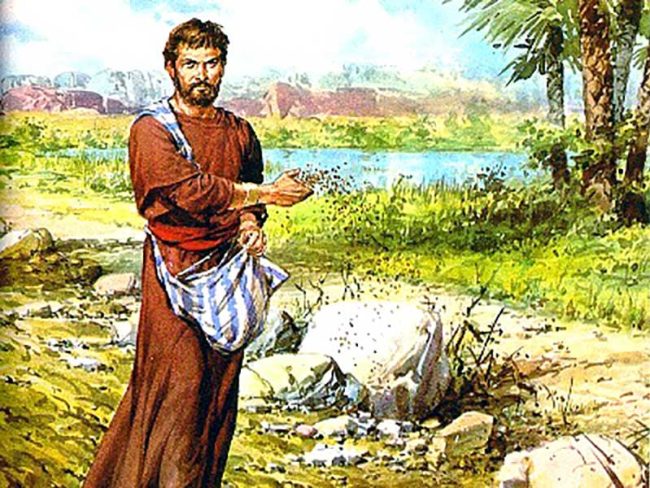「疑わずに信じるということ」
聖書箇所;マルコの福音書5:35~43/メッセージ題目;「疑わずに信じるということ」 私たちにとって、信仰が大事であることは常に意識している。しかし、その信仰を、いざというときに発揮できるか、それが私たちに問われている。いざというときに「恐れないで、ただ信じている」信仰を働かせることができるならば、その人は幸いである。 今日の箇所、会堂司ヤイロとイエスさまの箇所だが、ヤイロが何としてでも急いでイエスさまに、娘のために来ていただきたいとせかしても、群衆が押し寄せてなかなか先に進めなかったうえに、長血をわずらっていた女性をそのまま去らせず、わざわざケアすることさえイエスさまはなさった。そうこうしているうちにどんどん時間は過ぎ、ついに、ほんとうに娘は死んでしまったという知らせを聞くに至った。 こうなったらもう、イエスさまにいらしていただくには及ばないと思うだろうか。しかしイエスさまはおっしゃる。「恐れないで、ただ信じていなさい。」この話は、マタイの福音書、ルカの福音書にも記録されているが、マタイの福音書を読むと、「恐れないで、ただ信じていなさい」とイエスさまがおっしゃった後で、「そうすれば、娘は救われます」と続けていらっしゃる。 イエスさまは、単に娘を生き返らせようとなさったのではない。いや、「生き返らせる」ということ自体、「単に」では済まないくらいすごいことなのだが、もし仮に生き返ったとしても、その魂がイエスさまによって「救われる」ことなく、ついにはほんとうに死んでしまったとするならば、何にもならない。事は娘の「救い」にかかわることだった。「あなたが最後まで信じるならば、あなたの娘は永遠の死から救われて、永遠のいのちに至る救いに導かれる」、これをイエスさまはおっしゃりたかったのである。 つまり、ここでイエスさまに信仰が問われていたヤイロは、2つの点で信仰を働かせる必要があった。ひとつは、娘が生き返るという信仰、そしてもうひとつは、娘が救われるという信仰である。しかし、イエスさまにあっては、この2つの信仰は、本質的にはまったく同じものであった。イエスさまによって復活するということは、イエスさまから永遠のいのちをいただくということである。また、その復活を起こされるというイエスさまのみわざは、旧約以来預言されてきたとおり、時至って、神の国がこの地に来たらされたという、終末を告げるみわざであった。 私たちはよく、自然災害や戦争、経済的不安といった世相を見て、いよいよこの世界は終末かなどとうろたえがちなものだが、終末というものは、2000年前にイエス・キリストが力ある身わざを持って神の国をこの世に来たらせられて以来、この世界は終末にすでに突入していることを、忘れてはならない。要するに、いま現実に終末を生きている、それが私たちなのである。 そういうわけで、このヤイロの娘がよみがえることは、人を救って神の御国に導き入れるという主の御業がなされることにおいて重大な意味を持っていた。また、イエスさまによって神の国がこの世に実現していることを示すことにおいて、重大な意味を持っていた。きわめておごそかなことだった。 このことは、イエスさまが十字架と復活をもって、完全に満天下に主のみこころ、イエスさまが統べ治める神の国を実現されるまでは、まだ秘密、奥義の段階だった。それでイエスさまは、娘の両親であるヤイロとその妻、そして十二弟子の選抜メンバーであるペテロ、ヤコブ、ヨハネだけを伴われて、娘のいるところに行かれたのだった。 しかし、そこで待ち構えていた者たちは、すでに葬式をおっぱじめていた。騒いだりする者、さめざめと泣いたりする者、いろいろである。しかし彼らに共通していえることは、それこそ「喪主」になるべきヤイロがなぜここにいないで、イエスさまのところまで向かって行ったか、そのヤイロの信仰を理解していなかったことである。果たして、彼らはイエスさまのことも理解していなかった。イエスさまに対して信仰を働かせるなど、望むべくもなかった。 彼らの反応はどうだったか? イエスさまが、この娘は「死んだのではなく、眠っている」のだとおっしゃったとき、イエスさまのことを「あざ笑った」のである。あざ笑った理由はいろいろ考えられるだろう。娘が生きているうちに来ることもしないで、何を言っているのか、という思いもあったかもしれない。しかしはっきりしていることは、イエスさまのみことばよりも、目の前に存在するヤイロの娘の「死」というものが、よほど彼らにとってリアルな現実だった、ということである。 イエスさまのみことば、特に復活に関するみことばを信じることは、私たちクリスチャンにとって必須の信仰である。毎週、礼拝のたびに唱和している「使徒信条」、その締めくくりのことばは、「とこしえのいのちを信ず」である。しかし、私たちはこの「使徒信条」で告白しているそのままに、世においてはだれもが死ぬ、私たちの知っているかぎり、生き返った人はだれ一人いない、という現実を前にしてもなお、人の「死」より、「復活」のほうがリアルな現実であることを、なお信じていられるだろうか? 残念なことに、キリスト教会を標榜するグループに属する人たちの中に、復活を信じられない人がいる。復活を信じられない人はむなしいと、第一コリント15章にはっきり書かれていることを考えると、彼らの信仰はとてもむなしいもので、さらに言えば、神のことばである聖書をまともに信じていない信仰でもある。これはさらに突き詰めると、イエスさまの復活さえも信じないということになってしまう。しかし、ご自身復活されない、そして人も復活させられないイエスさまは、ほんとうにイエスさまなのだろうか? 私たち、水戸第一聖書バプテスト教会は、「保守バプテスト同盟」という群れに属している。何に対する保守なのかといえば、かつてアメリカを席巻し、福音主義に対して大いなる脅威となっていた自由主義神学、それこそ、聖書を人間的な自由で解釈するあまり、聖書を批判的に読むのも自由、したがってイエスさまのこのよみがえりに関する記述も、あり得ない、神話だ、と読もう、とするような聖書の読み方をする、そんな自由主義神学に対する、本来の「聖書は神のことばである」という前提で聖書を読んで学ぶべきという意味での「保守」である。私たちはそのように、信仰の戦いを繰り広げた信仰の先祖につながる群れの一員として、疑わずに聖書を読む、疑わずにイエスさまのみことばを信じる者となりたいものである。 ただし、疑わずに聖書のみことばをお読みするのは、簡単なことではない。なぜならば、私たちはどこに行っても「常識」というものに囲まれて生活しているからである。そもそも、うちの教会は、「進化論」という「常識」を、聖書を前提にして批判するところから形成されてきた群れであり、私たちはこの世が金科玉条のように大事にしている「常識」というものが、聖書の光に照らせばいかにあてにならないか、ものによっては受け入れるべきではないかを知りながら生活している存在である。 それでも、イエスさまのみことばを受け入れることに困難をおぼえる場合がある。世の人は言うまでもない。イエスさまが実際になさった復活のみわざについても、信じない、でたらめだと言ってはばからない。私たちがすることは、そんな彼らのレベルに合わせて信じてもらおうと、自由主義神学のような妥協をすることだろうか。そうではないはずである。あのときイエスさまは、「娘は眠っているのです」というその「真意」を、説明して、彼らを説得して、そのまま葬式を進めるに任せただろうか? そうではない、復活させるという、実際のみわざをなわったわけである。神の国はことばにはなく、力にある、それをイエスさまは実際になさったのである。私たちが信じるべきは、ことば遊びのつじつま合わせではない、実際にイエスさまが御力をもって行われたそのみわざを、そのまま信じることである。 イエスさまはそのように、どのような現実の中にあろうとも、恐れずに信じる者に、みわざを示してくださり、みこころの奥義を示してくださって、ますます、キリストに似た者へと変えてくださる。私たちはそのような中で、予想をはるかに超えるみわざを見せられて、そのようなみこころを示されて、驚くばかり。 イエスさまがそのような場に私たちを招いてくださっていることを感謝しよう。いまこの場、礼拝の場は、復活のイエスさまが、私たちのことを復活のいのちへと招き、導いてくださっているという、奇跡が実現している場である。わかる人にはわかる。私たちもわかる者にしていただこう。わかる者にしていただいているなら、心から感謝しよう。 さて、イエスさまはこの復活のわざを行われたとき、人々には黙っておくようにと、釘を刺された。イエスさまをあざ笑うような者たちが、このわざを見れば、あるいは態度を変えるかもしれない。しかし、それはしょせん、世にいうところの「手のひら返し」のレベルであって、本質的にイエスさまのことを理解するようになるわけではない。彼らが興奮して、「この方こそユダヤの王だ!」とイエスさまのことを祭り上げたならば、イエスさまが十字架と復活をもってユダヤ人の王、いな、すべての王の王となられるという神のご計画は、崩壊しかねなくなる。 イエスさまのこの戒めは、私たち、特にクリスチャンが少ない日本の者たちにとって、教訓とならないだろうか。何か大きなみわざが行われないものか。そうすれば多くにひとが救われて、イエスさまの名は世間にとどろくのに。私も以前は、リバイバルを祈り求めていた大学生のころなどは特に、そのムーブメントを導いていた先生方の意図されていたところに反して、そのような一発逆転のような考えでリバイバルを祈らなくもなかった。 しかし、イエスさまが神の国を成し遂げられることは、人の考えや期待に応じてのものではない。神のみこころと時はしばしば人間のそれとは一致しないが、すべてを超えて働かれる神さまのみこころと時は、人間のすべての考えにまさって働く。 とはいっても、娘が生き返ったのは事実で、その日以来、娘が元気な姿で人々の前に姿を現したならば、それがイエスさまのみわざによることを、イエスさまのことをあざ笑った人たちもさすがに認めるしかなかった。マタイの福音書によれば、この話は一帯に広がったとある。イエスさまは確かに奇蹟を秘密のうちに行われたが、そのうわさが一帯に広がることまで計算に入れないでみわざを行われたわけではない。これは、神の奥義を顕す奇跡の記述に満ちている聖書が、クリスチャンにとどまらず、一般にも普及して、彼ら一般人もイエスさまの奇跡そのものを知ることができるのと同じである。 その中から、イエスさまのみわざに、イエスさまが神の御子であると認め、イエスさまを信じる人が起こされもするし、そのみわざはでたらめだ、神話だという人もいる。イエスさまを信じない人がいようとも、私たちが聖書を教会だけの内輪の財産にしないで、人々に伝えて回るのも、そのように救われる人が現れる可能性があるからである。 しかし、忘れてはならないのは、このにぎやかし、野次馬のごとき群衆は、イエスさまが実際にみわざを行われる場面に立ち会える栄光にあずかれなかった。しかし、弟子ならばイエスさまのみわざに立ち会える。そして人々にイエスさまの復活を宣言し、人々を永遠のいのちへと導く働きに用いていただける。群衆と弟子を分けるのは、この信仰があるかないかである。私たちは群衆でかまわないと思っていてはならない。私たちはすべからく、弟子を目指し、弟子として生きるべきである。