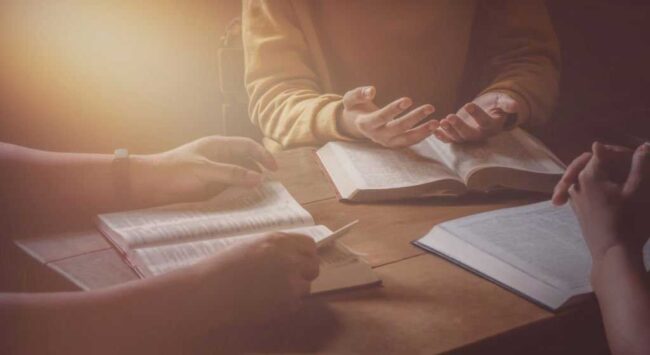婚宴の完成
聖書箇所:ヨハネの福音書2章1節~12節 メッセージ題目:婚宴の完成 昨日は何とすばらしい日だったことでしょうか! さだまさしさんの歌で「親父の一番長い日」という歌がありますが、私ならさしずめ、「牧師の一番長い日」でしょうか。私にとって結婚式の司式は、足かけ17年になる牧師生活において、初めてとなりました。そんな昨日は、ほんとうに長かった! 翌日の礼拝、どうしよう……? 種明かしを先にしておきますと、今日の礼拝メッセージは、もうかなり早い段階でつくっておいたものでした。また、先週に続いて狙っていたようですが、ヨハネの福音書の1章の連続講解をしばらくお休みしていて、それを今日から再開しようというタイミングで、なんとこの2章は、結婚式の場面から始まっています。結婚式の翌日に、結婚式のメッセージ、なんてタイムリーなんでしょう! イエスさまは、水をぶどう酒に変えられた。日曜学校の定番のメッセージ、鉄板のメッセージです。「イエスさまが語るなら 水が変わってぶどう酒になる」なんて歌を、振りつけつきでお友だちが歌うわけですが、だから、イエスさまってすごいね、イエスさまって何でもできるね、という、イエスさまが全能の神さまであることを教える、またとない聖書本文であるわけです。では、ともに学んでまいりましょう。 1節、「それから三日目」とあります。1章43節以下に書かれた、ピリポがイエスさまの弟子となり、ナタナエルをイエスさまに会わせたできごとの、それから3日目、ということです。カナはその、ナタナエルの出身地であり、イエスさまが過ごされたナザレのすぐそばにあります。 このカナで、婚礼がありました。婚礼はまず、婚宴が先になります。昨日の結婚式のように、日本では礼拝としての式が先にあり、それから婚宴となるのが普通ですが、ユダヤにおいては、婚宴が先です。婚宴は何日にも及ぶといい、そのため、婚礼の日取りはあらかじめ村中に知らせ、村中から人が集まる、村の一大イベントとなります。 そこにイエスさまの母マリア、そして兄弟たちがともにいました。ヨセフの名前が書かれていないのは、彼がすでに亡くなっていたことを暗示しています。ヨセフの家業は大工でしたが、大工というと、日本では材木で家を組み立てる人というイメージがあるかもしれません。しかしユダヤにおいては、大工とは石に鑿(のみ)を当てて作業する人です。ヨセフはそういう仕事をしていたので、仕事をするたびに大量の粉塵を吸い込み、公害病として問題になった「石綿肺」、つまり「中皮腫」のような状態になって、長くは生きられなかった可能性があります。 イエスの兄弟たちというのは、ヨセフとマリアの間に生まれた子どもたちで、イエスさまから見れば弟にあたる人たちです。「主の兄弟」ともいいます。男兄弟は4人の名前が聖書に記録されていて、このうち、初代教会の指導者であったことが確かなのは、ヤコブとユダです。ふたりとも、手紙類の著者として新約聖書に名を残しています。 ともかく、マリアや主の兄弟たちがその婚宴にいたことは、彼らがこの婚宴において、かなり大事な役割を果たしていたことを示しています。そんな婚宴に、2節にあるように、彼らにとっては長男であったイエスさまが、弟子たちとともに招待されていたわけです。イエスさまは、係累を断ち切って放浪の旅に出ていかれたわけではないことが、ここからわかります。 3節。この節は、「婚宴のぶどう酒がなくなった」ということ、そして、マリアがイエスさまに「ぶどう酒がありません」と言ったこと、この2つのことが語られていますが、ひとつひとつ見てまいります。まず、婚宴のぶどう酒がなくなるということは、何を意味しているでしょうか。ぶどう酒というものは、ユダヤ人にとって、喜びを盛り上げるために必須のアイテムでした。ぶどう酒のないパーティなど、ユダヤ人にはありえないものでした。 だから、婚宴の主催者である花婿は、威信をかけて、お客がどれくらいやってくるかを計算して、充分な分量のぶどう酒を準備しておくものです。しかし、予想もしなかったようなお客がぞろぞろやってくることもあり得ますし、酒好きなお客が好きなだけ飲んでぶどう酒のストックを減らしてしまう、ということも起こってくるわけです。しかし、理由はどうあれ、ぶどう酒がなくなってしまったら、花婿には、招待客もろくにもてなせない男、という烙印が押されてしまうことになり、彼は以後、カナの村でコソコソと人目を忍んで暮らすしかなくなります。こんなことなら結婚式なんてやらなきゃよかった、というレベルの大しくじりです。 万事休す、となったとき、マリアはイエスさまを捕まえ、「ぶどう酒がありません」と言いました。どうもマリアは、給仕係を責任をもって束ねる立場にあったようです。そんなマリアとしても、ぶどう酒がなくなるのは真っ青になることです。どうしよう……そうだ、イエスに言おう! 当たり前の話ですが、マリアは、イエスさまがただの息子ではない、神の子だ、ということを、だれよりもわかっていました。なにしろ、身ごもったプロセスがプロセスです。その後も、12歳の日にイエスさまがエルサレム神殿にとどまり、神さまを「父」とお呼びしたことを、マリアが心に留めたということが、聖書に記録されています。マリアがイエスさまを全能なる神の御子と思わされることは、おそらくその聖書に記録されていることにとどまらず、子育ての中で、一緒に暮らす中で、何度となく体験してきたことでしょう。 しかしマリアのこのことばは、イエスさまのことをもちろん、全能の神さまと見込み、なんとかしてください、という、願いが込められていた一方で、母親が息子に対して、あなたが神の子ならなんとかしなさいよ、という思いもまた込められていたと言うべきでしょう。なぜならこの箇所には、「マリアは」ではなく「母は」と書いてあり、マリアは「母として」イエスさまに言いつけたことがほのめかされているからです。 これに対するイエスさまのおことばは、聖書の読者には、なんとも意表をつくイメージを及ぼさないでしょうか。4節です。「するとイエスは母に言われた、女の方、あなたはわたしと何の関係がありますか。」えっ、イエスさま、お母さんにそんな言い方していいの! でも、イエスさまがそうおっしゃるんだから、間違っているわけじゃないんだよなあ……いろいろ、もやもやするところでしょう。 まず「女の方」ですが、このことばがどこか突き放したような冷たいニュアンスを読者に対して持っていることは、日本語の聖書だけではなく、韓国語や英語の聖書も同じようです。しかし、このことばは、原語の意味に照らせば、女性に対する一定の敬意を込めた表現であり、日本語の聖書の字面から感じるように、けっして冷たいわけでも、突き放しているわけでもありません。イエスさまは一定の敬意をこめて、お母さんマリアに呼びかけていらっしゃるわけです。 しかし、お母さん、ではなく、女の方、と呼びかけられたことには、なお疑問が残るでしょう。そのうえ、「あなたはわたしと何の関係がありますか」ときています。イエスさまがこんな、一見するとにべもないお返事をなさったのは、そのあとに続くみことばにその理由が語られています。「わたしの時はまだ来ていません。」この「時」とは、イエスさまがメシア、キリストとして栄光をお受けになる、その「時」です。しかし、ほんとうのところ、イエスさまはどのようにして、栄光をお受けになるのでしょうか。究極的には、十字架をもって御父への従順を果たすことで御子としての栄光をあらわされることです。そしてイエスさまのこの栄光は、復活、そして、再臨において、極致へと達します。 その、イエスさまにとっての「時」は、すべて、父なる神さまの「時」への従順をもって実行されます。御父の「時」に沿わないイエスさまの「時」というものはありません。ですからイエスさまは、母親に対して「女の方」とあえておっしゃることによって、ほんとうに従うべきは母親の時ではなく、神さまの時である、言い換えれば、母親のことばではなく、神さまのみことばに従うべきであることをお示しになったのでした。 マリアはこのことばに、イエスさまのことを、自分の息子である以前に、神の御子であると認めるしかありませんでした。しかし、そのマリアのことばは振るっていました。3節のみことばです。……マリアはまず、イエスさまをもはや自分の息子のように、また、ことばはあれですが、自分の所有物のようにみなすのをやめていました。行いをもって従順にお従いすべき神さまと見ていました。この、マリアのことばの変化は、マリアがイエスさまを従わせようとしていたが、イエスさまにマリアが従うようになった、という、ほんらい、神と人との間にあるべき関係へと変えられたことが示されています。 この変化は、私たちが信仰生活を積み重ね、祈りとみことばを通じてのイエスさまとの対話を重ねていくうちに体験するものです。私たちは最初、神さま、イエスさまに対し、自分の願いをかなえてほしい思いで、あれもしてください、これもしてください、という態度で祈ります。それはたしかに、主が全能であることを信じているからそう祈るのですが、主のみこころは実際どうなのか、ということを、あまり考えていません。しかし、みことばを学びつづけることで、神さま、イエスさまのみこころを知るようになったならば、そういろいろなことをやたらと祈ることをしなくなります。むしろ、神さまのみこころは何か、何を願っていらっしゃるか、何を喜んでくださるか、それをひたすら学ぼうとし、そのみこころに従順になれるようにと、祈りが変わってきます。その祈りの生活のほうが、あれこれ願う祈りの生活よりも、はるかに豊かで意義深いものであることは言うまでもありません。 マリアはまた、自分の差配している給仕の人たちを、イエスさまのみことばに従順になるようにさせました。そうです、主のみことばに従順になることは、単に自分個人が従順になることにとどまりません。自分が影響力を持っている人を、主のみことばに対して従順になるようにすること、これぞ、ほんとうの意味での従順です。 6節をご覧ください。ここには、ユダヤ人のきよめのしきたりに用いられる水がめがありました。律法の民であるユダヤ人は、外から家の中に入るときには道の埃で汚れた足を洗ったり、食事のときには手を洗ったり、器を洗ったりと、とにかく洗います。それは、物理的な清潔ということ以上に、宗教的なけがれからのきよめという意味がありました。この水がめを水で満たしなさい、というのです。この水がめはひとつがざっと、80リットルから120リットルは入る大きさです。それが6つですから、どんなに少なく見積もっても500リットルにもなります。このみわざが、単に水を変えてぶどう酒とするということだけなら、わざわざそんな大量の水を汲んでは水がめに入れ、汲んでは水がめに入れ、なんてことをする必要はないでしょう。なんでしたら、何もないところからぶどう酒を出してみせたってよいわけです。何といってもイエスさまは全能なるお方なわけですから。 そうなさらず、この、ユダヤ人のしきたりに欠かせない水がめをわざわざお用いになったのは、理由があったというべきです。イエスさまの弟子たちは、きよめの洗いをしないで食べ物を口にしたことから、パリサイ人、律法学者たちにとがめられました。しかしイエスさまはそのように非難する宗教家たちに対し、あながたがたこそ神の戒めを破っている、と逆に非難されました。そのときイエスさまは、預言者イザヤのことばをお用いになりました。「この民は口先ではわたしを敬うが、その心はわたしから遠く離れている。」 これまでの時代、ユダヤ人は、神の律法さえ守り行えばそれでよし、と考えていました。しかし実際のところ、律法を守り行おうとするところには、かえって神さまから離れているという、神の民にあるまじき実際の姿が、あぶり出しになるだけでした。 そのような人間は、きよめてもきよめても、根本的にきよくなることはできません。きよめのしきたりに用いる水がめに満たした水は、結局のところ、きよめることができないのです。それが、イエスさまがおいでになる前の、旧約の時代の民の姿でした。 しかし、イエスさまはこの水を、ぶどう酒に変えられました。このみわざを行われたことは、マリアにおっしゃったおことばと矛盾するのではないか、という疑問については、あとてあらためて触れますが、とにかくイエスさまはこの水を、ぶどう酒に変えられました。 アモス書9章13節のみことばも語るとおり、聖書的に言えば、ぶどう酒とは神さまの祝福の象徴ですが、主イエスさまご自身はぶどう酒というものを、神と人を和解させるためにご自身が流される血潮になぞらえていらっしゃいます。十字架の血潮が注ぎかけられることこそ、人にとって最高の祝福であったのです。人のけがれというものは、きよめの水を用いても根本的にきよめることはできませんでした。しかし、イエスさまの十字架の血潮は、すべての罪とそのけがれから、すべての人をきよめます。イエスさまがこの水がめの水をぶどう酒に変えられたことは、きよめの水できよめることが限界だった旧約時代が、まさしくイエスさまご自身の御手で幕引きされたことを意味していました。 しかも、そのぶどう酒というものがどんなものだったか。8節から10節です。宴会の世話役、すなわち、総責任者は、このぶどう酒を口にして驚きました。こんな良質のぶどう酒を最後のお楽しみに取っておいたとは、あなた、なかなかやりますな! 花婿をべた褒めしました。この世話役の言うとおり、酔いが回ったら、質の悪いぶどう酒を出されてもそれと気づきません。だから、よいぶどう酒から先に出すのが常識ですし、そうしないともったいないから、あとによいものを出すということはしません。ところがこの、イエスさまがおつくりになったぶどう酒ときたら、すっかり酔った人にもはっきりわかるほど、段違いに質のよいものでした。 これもまた、イエスさまの来たらせられる時代は以前のものにまさって素晴らしいことを教えています。ぶどう酒がやがて質の悪いものに取って替わられてもそれが当たり前なように、どんなに新しく、いいものが生み出されたと喜んでいても、どんなものもやがて陳腐になります。しかし、イエスさまは以前の罪によって古びるしかなかった人間を、その世界を、ご自身の救いによって新しく変えてくださいます。けっして滅びることのない、永遠のいのちに生かしてくださいます。そして終わりの日にこの世界に再臨してくださり、私たち主の民、教会を、花嫁として迎えてくださいます。 そう、神さまは世のはじめ、人を男と女に創造されましたが、エバがアダムから取られ、アダムがエバと対面したとき、それは人類最初の結婚式であったと言えましょう。そして、世の終わりも結婚式で大団円です。そう考えると、人類の歴史、神の民の歴史は、結婚式に始まり結婚式に終わります。そうだとすると、11節のみことばにあるとおり、イエスさまが結婚式という場で最初のしるしを行われ、ご自身の栄光を顕されたということは、主のみこころという点で、また、人類の救いのみわざという点で、これほどふさわしい場所はほかになかったとも言えるわけです。イエスさまがこのとき、ここで最初のしるしを行われたのは、マリアに頼まれたから、以上に、このときこそ、御父のみこころにお従いして、ご自身の栄光を顕すべき時だった、ということです。 昨日、私は、牧師先生のお姿に、イエスさまを見ました。そして、ウェディングドレスに身を包んだ姉妹のお姿に、終わりの日にイエスさまに嫁ぐ教会を見ました。これが、イエスさまの栄光だったのだ。カナの婚宴で、宴会の世話役はそのぶどう酒をつくったお方がイエスさまであることを知らず、ひたすら花婿のことをほめました。花婿とは、終わりの日に花嫁なる教会を迎えるイエスさまの象徴。イエスさまはそんな、ご自身の存在をこの地上で現す花婿に、あえて裏方となることによって花を持たせてあげたとは! なんてカッコいいんだ! そう思いませんか! しかし、やはりほんとうの花婿は、イエスさまです。この、水がぶどう酒に変えられるしるしが、イエスさまがまことの花婿として、世の終わりに究極の栄光をお受けになることを示しました。このみわざを目撃した弟子たちは、イエスさまはやはり神の子キリストだったのだと信じ受け入れました。そう、このように、人がイエスさまを信じるということ、これぞ、イエスさまの栄光が顕される、ということです。 すでに弟子になっている者が、イエスさまを信じる? 信じたから弟子になるんじゃないのか? 順番が逆じゃないのか? そう思いますか? しかし、こういうことは往々にして起こることです。弟子とは、イエスさまについていく人です。弟子というものをそう定義したら、キリスト教の幼稚園や保育園に通い、礼拝をささげているちっちゃな子どもたちも、立派にイエスさまの弟子といっていいと思います。彼らは幼いなりに、イエスさまの言うことを聞こうとします。また、子どもではなくても、何かのきっかけに教会通いを始める求道者も、弟子の歩みを始めていると言えるでしょう。 しかし、やがて彼らも成長するにつれ、イエスさまを受け入れるべき時がやってきます。イエスさまが救い主であることをみことばからきちんと理解するには、それなりに求道生活を送っている必要があります。わからないなりにみことばを学び、わからないなりに礼拝に出席し、わからないなりに聖徒の交わりに加わる。これは立派に、弟子の歩みです。そこから、みことばをしかるべく理解し、イエスさまを信じるに至るのです。 この、弟子として歩む意志を明確に持っている人は、確実に成長します。昨日、ウェディングドレスに身を包んだ姉妹は、2年前の4月、はじめてうちの教会にいらしたときから、もう明確に求道心をもち、真面目に主の弟子としての歩みをしていこうとしていました。 先週のみことばにあるとおり、行って、弟子としなさい。そう、弟子とすることから、人々を救いに導き、その救いにとどまらせるべく、みことばを教えるのです。弟子として歩んでも、イエスさまのことをほんとうに信じられる人はかぎられています。しかし、イエスさまの弟子としての歩みをどうしても続けたい、なぜならば、イエスさまこそが救い主だからだ、そう信じて、イエスさまにしがみつく人たちがひとりでも起こされるとき、その人が主のからだなる教会のひと枝に加えられるとき、イエスさまはご栄光をお受けになります。その、主のからだなる教会もろとも、救われた主の弟子たちがイエスさまのもとに嫁入りするとき、主の栄光は最高に輝くのです。カナの婚宴を完成させられたイエスさまは、終わりの日、この世界を完成してくださいます。その日を待ち望みましょう。