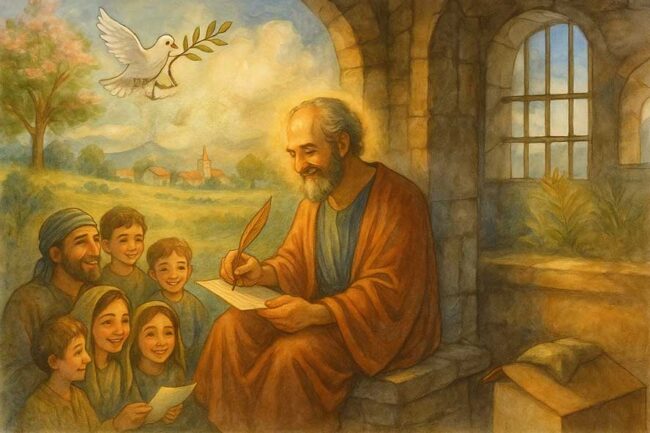万軍の主の御名によって
聖書箇所:サムエル記第一17章41節~58節 メッセージ題目:万軍の主の御名によって 今日は今年最後の礼拝となりました。みなさまにとりまして、今年はどんな年になりましたでしょうか? 私はこの年の終盤になって、ダビデのデビューにまつわる箇所からみことばをお取り次ぎしながら、主によって備えられた主の器はいかにあるべきかを教えられました。 私たちもいろいろな戦いを体験しています。家庭であれ、職場であれ、学校であれ、地域社会であれ、自分の思いどおりにするにはあまりに難しい課題にぶち当たったりすることがしばしばあるものです。人間関係かもしれません。新しい技術を取得することかもしれません。あるいは、自分自身の健康という問題であったりするかもしれません。 しかし、私たちは、自分にとっての戦いというものの本質を見失ってはなりません。みことばは語ります。「私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいるもろもろの悪霊に対するものです。」(エペ6:12)してみますと、私たちの闘う相手は、人でもなく、ましてや自分でもなく、悪魔、また悪霊であることがわかります。 私たちはときに、例えば職場などで、面倒くさい人、やたら威張る人、いやな気分にさせる人を「敵」と見なしたりはしないでしょうか? しかし、みことばによれば、そういう人たちはどんなに、私たちにしてみれば、不敬虔、不従順、不信仰なように見えたり、感じられたりしたとしても、「敵」ではないのです。「敵」は、その背後に働いて、私たちを攻撃するサタン、そしてその手下である悪霊どもです。 そういうことからも、だれかのことをさばいたり、悪口を言ったりするということは、私たちクリスチャンには似合いません。その人が悪いのではなく、その人を操るサタンならびに悪霊どもこそが悪いと見なし、そういう、悪い感情を抱かせてしまう人々に対する、そのマイナスの感情は、手放してまいりたいものです。 そこで、私たちの敵がサタンであるということはわかりましたが、それではどのように戦うものなのか・・・・・・今日の箇所は、そのことを私たちに教えてくれています。これを、5W1Hで解いて考えてみましょう。 まずはhowです。大前提として、ダビデは「万軍の主の御名によって」ゴリヤテに立ち向かっています。ダビデはたしかに戦場にいましたが、もとはといえばそれは、戦うためではありません。お父さんのお使いで、兵隊に食べ物の差し入れをして、従軍しているお兄さんたちの安否を知って、お父さんのもとに便りを持ち帰るためでした。だから、着ているものにしても、簡素な服装でしかありません。 しかし、ダビデはいざ戦うとなったら、それで充分でした。彼は羊飼いの服装、それこそ、労働のための簡素な服装でも、クマやライオンのような猛獣が羊の群れに襲いかかろうものなら、それに飛びかかり、やっつけていました。素手で打ち殺せたというから大したものです。要するに、私たちが想像するような、よろいかぶとに盾と剣を帯びた古代の兵士のような格好などしなくても、充分に戦えたのです。彼にとって武器などは、羊飼いとして持ち歩いていた石投げで充分でした。 しかし、彼は丸腰ではありませんでした。彼には、何よりもすごいものがありました。それは「万軍の主の御名」です。これはどういうことでしょうか? 人間の大軍団など到底太刀打ちできない、全知全能なる、父なる神さま、御子なるイエス・キリスト、聖霊なる神さまの三位一体の神さまが、天の大軍勢を率いて、ダビデをとおしてゴリヤテとその背後にある神に敵対する勢力に立ち向かい、戦ってくださる、ということなのです。これほどの力、無限の力をいただいているわけですから、ただ見栄を飾る以上のものではないサウルの武具など、全く必要ありません。 では、who、だれが戦うかを見てみましょう。昨日、新たな宣教の場所に旅立ってゆかれた金先生が繰り返しおっしゃっていたことを、思い出していただきたいのです。私たちクリスチャンは、実はすごい存在であるのだと。私たちのうちにイエスさまがおられるということは、第三の天にいますイエスさまが、ご自身天に至るはしごとして私たちとつながり、天におられると同時に、私たちのうちにおられるのだと。だから私たちは絶えず、天の御力と祝福をいただいているのだと。 そして、イエスさまがうちにおられる以上、聖霊なる神さまがうちにともにおられ、父なる神さまがうちにともにおられるのだと。三位一体の神さまがうちにおられるのです。いやはや、私たちはどれほどすごい存在なのですか! このお方が、ダビデをとおして戦われ、勝利してくださったように、私たちをとおして戦ってくださるのです。当然、私たちは勝ちます。「彼らは子羊に戦いを挑みますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。子羊は主の主、王の王だからです。」(黙17:14)ときに、負けた、と思えるようなときでも、主が戦ってくださるかぎり、私たちは勝利しているのです。 しかし、万軍の主の御名によって戦うと、私たちが口にするとき、問われるのはその動機です。私たちはもしかして、どこかで、自分のために、名誉ですとか高い地位ですとか、豊かで安定した暮らしですとか、そういったことのために、主の力を「動員」するかのような態度でいたりはしないでしょうか? それは大間違いです。そういうことに「霊的」な力を借りようとする生き方は、「宗教」にすぎません。私たちキリスト者の生き方はそういうものでは決してありません。主が主体であり、私たちは主に用いていただくのです。 神さまがサムエルを遣わされ、ダビデに油が注がれて以来、主の霊がダビデに激しく下るようになりました。それは、ダビデの主人がか弱い少年である自分自身ではなく、世界の何よりもお強いお方、主が生きてくださるという生き方です。パウロのことばのとおりです。「もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。」(ガラ2:20)しかしそれは、自分の古い人がキリストとともに十字架につけられて、もう死んでいる、生きているのは復活のキリストのいのちである、ということです。 ゆえに、私たちの戦いは目に見えるものが相手ではありません。目に見えるものの背後にうごめく悪しき存在、目に見えるものを操る悪しき存在、そういう邪悪な存在と戦うべく召されています。この戦いは主の戦いです。主が戦ってくださいます。主の戦いに、私たちは用いていただくのです。 その戦うダビデ、彼は神の霊の臨む、神の人です。そのダビデはなぜ戦うのでしょうか? Whyを問います。それは、ゴリヤテによってイスラエルに浴びせられた、その恥辱をイスラエルから取り除くためです(17:26)。 ダビデが問題にしたのは、イスラエルがゴリヤテを前にして、情けなくも震え上がっているからではありません。ゴリヤテがそのようなイスラエルのことを、ペリシテの神々の名により呪い、馬鹿にすること、それによってイスラエルの神が、あたかもペリシテの神々よりずっと弱く、また情けないもののように扱われていること、それを問題にしたのでした。 感情というものは、たしかに聖書のみことばという事実、そしてそれが事実にして真理であるという信仰に伴って生じるものであり、感情に振り回されることは信仰生活とは言えません。しかし、聖霊の臨む人、ゆえに神との交わりをつねに喜ぶ人には、ひとつの感情が伴います。それは、神さまが無視されること、神さまが馬鹿にされることには、耐えがたい怒りの感情を抱く、ということです。 ヤコブの手紙1章20節で戒められているとおり、「人の怒りは神の義を実現」しません。私たちにとっての怒りというものは多くの場合、みこころにかなわない肉的な感情の現れに過ぎないものです。しかし、それは、私たちの中から湧き上がる怒りの感情を何でもかんでも否定すべきだ、ということではありません。パウロにしても、アテネの町が偶像でいっぱいなことに怒りを覚え、その感情はパウロを福音宣教へと促しました。これは、持つべき怒りでした。 私たちが怒るとき、その怒りが正当か不当かは、聖霊なる神さまが教えてくださいます。アテネにおけるパウロの怒りは正当でしたが、神さまがニネベに悔い改めのみわざを起こされたことに対する預言者ヨナの怒りは不当でした。私たちの抱く怒りが主にあって正当か不当か、それは、聖書を読めば客観的にわかることです。 普段から祈りつつ聖書をまんべんなく読むことを心がけていれば、私たちは聖霊に導かれ、いざ、心に怒りを覚えるとき、それが主にある聖なる怒りであるならば、感情は高ぶっていても、心の奥底には不思議と平安があるものです。 そしてダビデは、神の御名をそしるゴリヤテに激しい怒りを燃やしましたが、その怒りはみこころにかなった正当なものであったゆえ、ダビデの心には不思議な平安、落ち着きがありました。普段、猛獣を狙って石を撃つように、ゴリヤテの急所という的を外さずに石を撃ち込みました。 私たちは怒ることも多いものです。何かあると、かっとなって、声を荒らげたくなったり、暴言を吐いたりしたくなる誘惑にさらされるものです。しかし、その怒りは果たして主から来る、正当なものなのでしょうか? 怒る私たちの心に、ほんとうに平安はあるのでしょうか? 逆に、明らかに主の御名が無視されるような状況を見聞きするとき、私たちの心はどうなっているでしょうか? 先週、私たち教会は、クリスマス礼拝をおささげする、素晴らしい時間となりましたが、そんな教会のことなど見向きもしないで、人々はクリスマスセールに行ったり、パーティーをしたり、デートをしたりします。昨今はクリスマスマーケットなんてものもブームになっています。でも、教会には行きません。そんなふうに、てこでもイエスさまに目を向けさせまいと日本人を操るサタンの存在とその働きに私たちはもっと怒り、この霊的な妨げをとどめてくださいと、もっと祈るべきではなかったでしょうか? こういうことには怒っていいですし、怒るべきです。切なる祈りはそこから出てきます。何が起ころうとも平然としているならばそもそも、いっしょうけんめい祈る理由がありません。怒るべきときに怒ってこそ私たちはキリスト者です。主の御名がけがされることに対する怒りから主に叫び求める、その祈りをもって、私たちは悪しき霊的存在と戦うのです。そしてもちろん、主が十字架と復活をもってすでに勝利してくださったゆえ、私たちはこの戦いに勝利します。アーメン! あとの3つにまいりましょう。「where」、彼はいきなり、戦場に放り込まれました。しかし、主の戦いをすることにおいては、羊の牧場だろうと、戦場だろうと、彼には同じことでした。任された羊のために猛獣と戦うことと、神の民なるイスラエル、ひいてはその主なる神の御名のためにゴリヤテと戦うことは、ダビデには同じことでした。いずれも、「神の栄光を現す場」という点で同じでした。 私たちの人生も、いろんな場面を経験しています。自宅、職場、行き帰りの車、買い物先、その他諸々、しかし、どこにおいても言えることは、私たちはどこにいても、「神の栄光を現す」戦いに置かれている、ということです。 そんな、無茶な、と思いますか? しかし、ほんとうのプロフェッショナルは、つねにどんなときも、自分がその立場に置かれていることを前提にあらゆる振る舞いをします。テレビや映画に出演するようなスターのプライベートがさらされてスキャンダルになることがやたら人の関心を引くのは、スターたるもの、いつ、どんなときも、スターとして振る舞ってほしいという人々の要求に応えることそのものが仕事であり、生き方であるからです。だから、スキャンダルがなくて高い人気を誇るスターはほんとうにすごいプロ意識を持っていることになります。 私たちはテレビに出ないかもしれませんが、スターです。神の栄光を輝かせる世の光であり、暗い世界を明るく照らす星だから、文字どおりスターです。そんな私たちが、世の光として主の光を輝かせないで済ませていい場所など、世界のどこにもありません。そもそも私たちの生活は、神さまの前に丸裸です。つねに神さまを恐れる前提で生きているならば、人前でつねに神の栄光を現すよい振る舞いをすることなど、まったく難しくないことになります。 ただ、こんなことを言っている私も、実はついこの間まで、そんなの理想論だ、と、心のどこかで思って、言いたくてもなかなか口に出せないでいました。しかし、このたび、金先生ご夫妻がいらっしゃり、ひと月にわたってお交わりをしたことをとおして、私の考えは完全に変わりました。どこを取っても主の光を輝かせる、そういう生き方はほんとうにできるのか! 驚きはやがて、確信に変わりました。私もまだまだですが、少しでも、つねに世の光として輝く生き方を実践していけるように祈っていこうと願うゆえんです。 サタンは、私たちの光を輝かないように妨げます。世的な生き方を諦めるな、肉的な生き方はいいぞ、霊的な生き方はダサいぞ、ささやきつづけて洗脳しにかかります。しかし「光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。」(ヨハ1:5)サタンはイエスさまにすでに、完全に敗北しているのです。だが、まだ負けていないかのように私たちをだます力はまだ残っています。いや、それどころか、サタンの方がイエスさまより強いという、偽りをまだまだ私たちに吹き込み、そのとおりだとばかりに私たちに振る舞わせる力さえまだ持っています。サタンを侮ってはなりません。イエスさまが完全に勝利してくださったことを、つねに宣言する必要があります。 「when」それは、神の時です。エッサイにとっては、ダビデをおつかいにやった時でしかありませんでした。しかし神の霊はダビデを奮い立たせ、おつかいの時を、戦いの時に変えられました。ダビデはこのとき、「いや、私は単に届け物をして、兄たちの安否を父に伝えるために来ただけですから・・・・・・」とは言いませんでした。ゴリヤテに戦って勝利したらどうなるかを兵士たちに聞いて回り、ついにはサウルに、闘わせてくださいと直訴しました。 神との交わりに生きる人は、神の導きを自分の事情や感情よりも優先させます。ヨハネの黙示録21章8節に、「臆病な人は、火と硫黄の燃える池」に投げ込まれる、つまり、地獄で永遠に滅びる、という意味のことが語られていて、ああ、私はクリスチャンのくせに、臆病だから、地獄に落ちるのかしら、と思ったりしていないでしょうか? もしそうならば、今日この瞬間から考えを変えましょう。「神は私たちに、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊とを与えてくださいました。」(Ⅱテモテ1:7)聖霊に満たされるとは、イエスさまに満たされ、父なる神さまに満たされることです。ものすごい力に満たされ、かぎりない愛に満たされ、それでいて品性に満ちた慎みが伴います。何かを怖がっているならば、それは古い人です。それはイエスさまとともに十字架につけられました。いまや力と愛と慎みの霊なるイエス・キリストの御霊なる聖霊さまが、私のうちに生きています。このことをつねに、確信をもって宣言するならば、恐れは逃げ去ります。大いなる力をもって人を愛せるようになり、しかしそれでいて、暑苦しいような押しつけがましさとは無縁の、魅力的な人になれます。それでこそ神の人です。 こういう人は大胆です。神の導きとあらば、自分のこだわりや常識にとらわれないで動けるようになります。しかしそれは傍若無人ということではなく、つねに周りの徳を立てながらの言動として実を結びます。まさに離れ業、それこそ「神業」です。ともかく、私たちは聖霊が臨む時、力を受けて、必ずその証し人となり(使1:8)、あらゆる戦いに勝利を体験します。その「時」に従って生きるために、つねに御霊の満たしの中で生きるものとしていただきましょう。 最後に結論、「what」、それは「主の戦い」です(47)。私たちは主の栄光を現す生き方をするために、あらゆる努力を傾けるのです。ただし、それは、私たちが自分自身をキリストに明け渡すところからすべては始まります。主の戦いは自分の頑張りでできるものではありません。自分の頑張りに主の御力の助けをいただこうとしてもいけません。主に明け渡し、主が私を用いて戦ってくださる、この境地に至れるように、祈っていただきたいのです。 私たちは何において戦っていますでしょうか? 私たちの目の前に立ち塞がっているものはなんでしょうか? その背後にあるサタンの存在を、私たちは見極め、主がそのサタンと戦い、勝利してくださるにおいて、私たちは自分を明け渡しているでしょうか? ダビデにできていたように、それこそ、ダビデが主とひとつになっていたように、私たちも主とひとつにしていただくならば、主が私たちを用いて、その悪しき存在に勝利してくださいます。